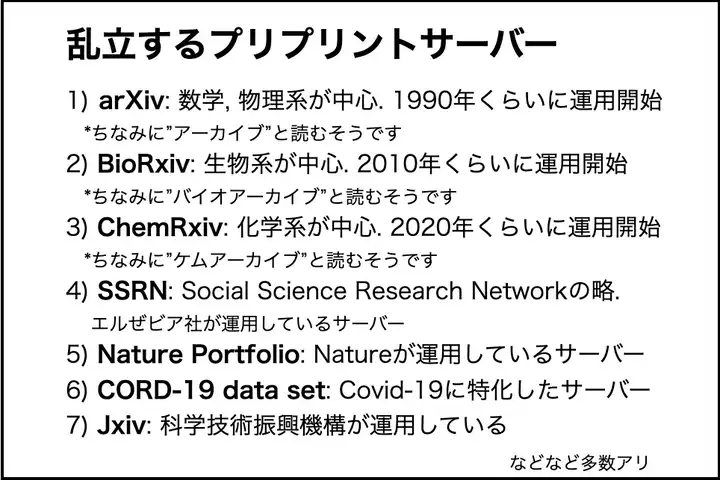プリプリント(日本語読みだとプレプリント)とは「特定のサーバーにアップロードされた誰でも読める査読前の原稿」のことです。
プリプリントの大義名分は「学術雑誌に掲載される原稿は、査読があるので投稿から掲載まで数ヶ月(ときには数年)かかる。成果を事前に見せることでフィードバックを受け、正式な投稿に向けた準備ができる」だそうです。
要は、査読なしで原稿をサーバにアップロードできるということです。そしてそれをタダで読めます。私は投稿前の原稿を不特定の人に絶対に見せないので、プリプリントは自分には関係ないなと思っていました。