指導教官としてすべきことは…
1.論文執筆のメンバーを集めること。
2.集めた人がそれぞれどのような役割を担うのか説明すること。
の2点です。
この記事で書かれた執筆の仕組みは、日本のほとんどの研究室でできていないのではないでしょうか。
トップジャーナルの書くための役割を分担できるだけでなく、どのように論文執筆の技術を継承できのかを理解できるので強くオススメします。
この記事では、私が体験したアメリカでよく用いられている論文を書く仕組みを紹介します。

知っていますか? 研究の本場アメリカではちゃんと分担して論文を書きます。論文を書く力や、研究費も重要ですが、「書く仕組み」が日本では特に軽視されている気がしています。
この記事では、私が体験したアメリカでよく用いられている仕組みを紹介します。
Nature系、Science系といったトップジャーナルの論文執筆を学ぶために非常に効率的な方法ですので、指導教員は意識してこの仕組みを導入すべきだと思います。
分担するメリットは、(1)教授が論文の質の向上だけに集中でき、(2)論文の書き方を継承でき、(3)研究不正を減らせる、の3点です。
指導教官としてすべきことは…
1.論文執筆のメンバーを集めること。
2.集めた人がそれぞれどのような役割を担うのか説明すること。
の2点です。
この記事で書かれた執筆の仕組みは、日本のほとんどの研究室でできていないのではないでしょうか。
トップジャーナルの書くための役割を分担できるだけでなく、どのように論文執筆の技術を継承できのかを理解できるので強くオススメします。
この記事では、私が体験したアメリカでよく用いられている論文を書く仕組みを紹介します。

指導教員としてすべきは、まずメンバーを揃えることです。論文の執筆には3人の異なる役割の人物が必要です。
まず1人目は、実験をやった人物で、研究の詳細を知る人物です。
次に2人目は、できたらNature系の論文を筆頭著者として書いた経験のある人物を指名しましょう。
最後に3人目は、Nature系でいうと5本くらい(共著者でもいい)書いていて、h指数だと50以上の人物が好ましいです。トップジャーナルを完成させるにはこれら3人が必要です。
もし指導教員がNature系を書いた経験がないなら、これら3人を集めるか、これら3人がいるグループに入って共同研究するべきです。
もし指導教員がNature系論文を書いた経験がないなら、共同研究によって論文を書く力をつけ、1人目もしくは2人目として仕事をするなかで、何十年かけて最終的に3人目の役割を担える人物になればいいと思います。

メンバーが集まったら、全員に役割を説明して書き始めましょう。
1人目の役割は、自分がやったことを書くことです。「draftを書く」役です。
2人目は、(1)1人目に「トップジャーナルの書き方を教える」ことです。普通の論文とトップジャーナルは全然違うので、その違いをちゃんと解説します。また(2)2人目は3人目に定期的に相談することで、1人目が書く「draftが間違った結論に進んでいないこと定期的に確認する」ことです。draftが完成した後にいきなり3人目にdraftを見せ、draftの内容を根本から書き換えなくてはならなくなった、といった失敗を避けます。
3人目の役割は、「draftから論文を完成させる」ことです。イントロで漏れていた書くべきことを修正し、歴史を振り返ったときに今回の結果がどんな意味があるのか解説し、少し先の未来を予言しましょう。2人目が論文の体裁を整えてくれたので、3人目は論文の内容向上に集中できます。

ただ、この3人で書く方法、いいことばかりではありません。しばしば起こる問題(私が体験した問題)が2点あるので、ここで紹介しておきます。
1点目は、「ケンカが頻発する」ということです。1人目は自分がやった実験で思い入れがあります。一方で、2人目は高インパクトファクターを目指すため、1人目が注目している部分とは違う点を強調して書きたがります。すると、両者の意見が対立して内容が決まりません。
私の場合はどうしたかというと、2人目に退出してもらい、1人目と3人目だけで完成させました。
しかしそれでも良かったです、1人目と2人目がケンカする中でdraftが洗練され、その洗練されたdraftは3人目が受け取っても論文を完成られるまでになっていました。
意見が対立するのは、完成が近づいているいいサインです。前向きになって論文を完成させましょう。

2つ目の問題点が、「3人目の研究者が大した添削をしない」ということです。
教員にはいろいろな教員がいます。研究の着眼点が優れている人、論文が書ける人、そして予算を取ってくるのが得意な人などです。
私達は誤まって、予算を取ってくるのが得意な人を3人目として任命してしまったことがあります。彼は世界的な権威なのですが、科学者としての実力が伴っていないから、彼には深く添削ができませんでした。
私たちはどうしたのかというと、新たな3人目を用意して書き直しました。随分と投稿が遅れました。
いきなりNature系の論文を書けるようにはなりません。知識や経験がない状態で努力するのはムダです。知識や経験がない状態で多くの研究費を使うのもムダです。
実験結果が良ければNatureに投稿できるわけではありません。そもそも、いい結果だと思った結果って、本当にいい結果なのでしょうか?高難易度の実験結果が、いい結果と勘違いしている可能性すらあります。知識をつけて実力のある人と書きましょう。このwebサイトでは知識を提供するため、全力でサポートします。
私はこの記事を通して本当に言いたいことがあります、それは「自分1人でやろうとするな」「筆頭著者と指導教員の2人だけで論文を書こうとするな」です。効率よく論文を書くため仕組みを作ること、経験を継承させる仕組みを作ること、論文の書き方のノウハウを重要ですが、執筆の「仕組み作り」も重要なんです。
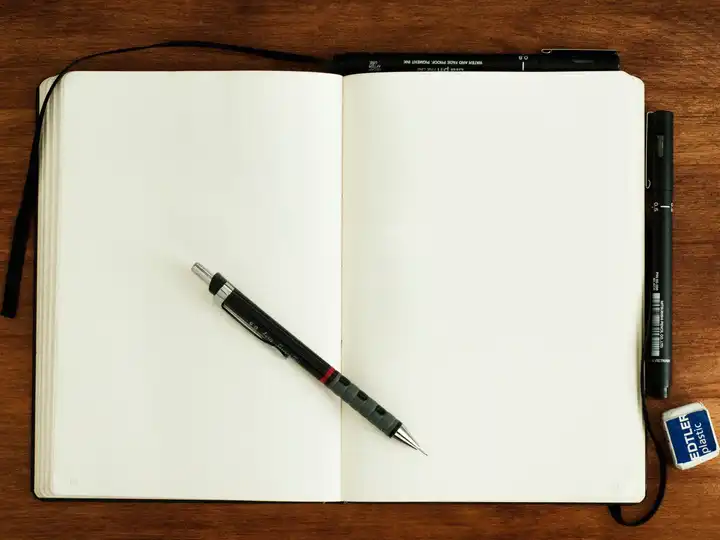
論文を書ける「仕組み作り」、本当に重要です。
指導教官としてすべきことは…
1.論文執筆のメンバーを集めることと、
2.集めた人がそれぞれどのような役割を担うのか説明することです。
論文執筆の仕事を3人で分担します。
1人目は、実験をやった人物で、研究の詳細を知る人物。
2人目は、Nature系の論文を筆頭著者として書いた経験のある人物
3人目は、Nature系が5本以上(共著者でもいい)書いていて、h指数だと50-100くらいの人物
要は、1人目は「draftを書く」。2人目は「トップジャーナルの書き方を教える」と「結論が正しいのを確認する」。3人目は「draftから論文を完成させる」です。
どうでしょう、「仕組み作り」本当に大切だと思いませんか? 筆頭著者に全てを任せてうまくいくわけがありません。自分の実力をつける仕組みを作りと、第一著者に実力をつけてもらう仕組みづくり、大切にするべきです。
・Nature Communicationsに採択された原稿に、解説を付けたテンプレートを作りました。Webサイトの解説した内容が実際にどう論文に反映されたか実例を見ながら理解できます。研究者として上を目指したい方、ぜひ参考に。
論文の解説付きテンプレート、なぜ重要なのか?
・論文の書き方は教わりましたか? このWebサイトに書いてある高インパクト論文の書き方をスライドにして1つにまとめました。論文の "型" を自習する教材として最適です。ぜひ参考に。
高インパクト論文の書き方をどう自習するか? [結論:この解説付きスライドを読もう]