私よりNatureやScienceを書いている海外の教授達のアドバイスをまとめました!!
それだけでなく、私が参加したセミナーでのエディターのコメントもまとめました!!
私より経験があるので、聞く価値のある人物です。しかし、根拠となる事実を確認できないため、もはやオカルトと呼ぶに相応しいアドバイスです。
Natureクラスになると採択率が極めて低いので、本当に正しいのかわからないコツが世の中に多く出回っています。
あなたは論文に関する以下の9つのオカルト信じますか?

少しでも論文を採択される確率を上げたいですか?
証拠はないけど、採択されやすくなるという "噂" を集めて書きました。
なんでもいいからとにかく改善したい方、必読です。
私よりNatureやScienceを書いている海外の教授達のアドバイスをまとめました!!
それだけでなく、私が参加したセミナーでのエディターのコメントもまとめました!!
私より経験があるので、聞く価値のある人物です。しかし、根拠となる事実を確認できないため、もはやオカルトと呼ぶに相応しいアドバイスです。
Natureクラスになると採択率が極めて低いので、本当に正しいのかわからないコツが世の中に多く出回っています。
あなたは論文に関する以下の9つのオカルト信じますか?

(1)「カバーレターに5年以内に一緒に論文を書いた人をレビューワ候補のリスト入れると即リジェクト」: エディターは著者同士が過去に一緒に論文を書いたのか一瞬で分かるソフトを持っていているそうです。知り合いをレビューワにさせて簡単に論文を採択させようとしているのがバレたらリジェクトということですね。
(2)「同じ大学の人間をレビューワ候補のリストに入れると即リジェクト」: 先ほどの理由と一緒です。友達にレビューさせたがっているように見えます。
(3)「業績リストを見たとき、大量の低インパクトの論文でリストが埋まっている研究者は即リジェクト」: 知らない論文誌にしか投稿してなかったら何の権威なのか全く分からないですよね。質の高い研究を遂行する実力なしと判断されても仕方ありません。業績リストを見た時、聞いたことがない論文誌に大量に論文を出していると、弱いパンチを必死で連打している様に見え、子供相撲を見ているような気持ちになってほっこりします。一方で私はアイビーリーグの先生の業績リストを見ると強烈な目眩がします。Natureシリーズが10個以上並び、業績リストをスクロールするのが怖くなり、見れば見るほど強烈な劣等感に襲われます。エディタも同じ気持ちなんだと予想します。逆に、弱パンチの教授はなんで今回いきなりNatureに出そうと思ったのか疑問です。
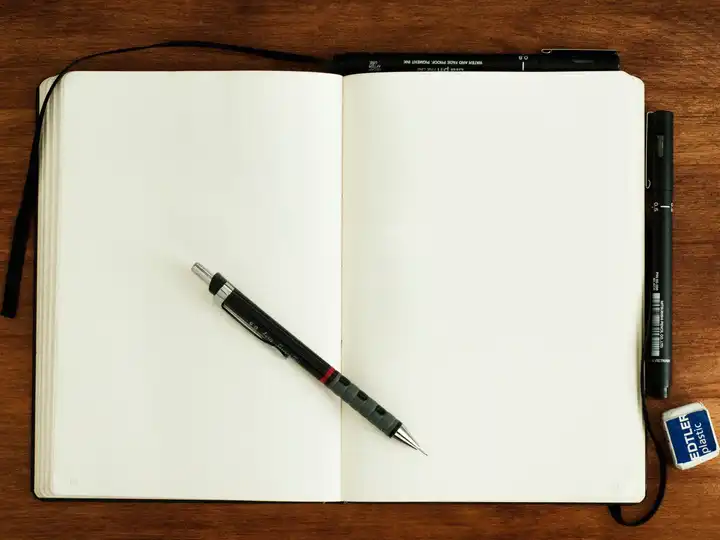
(4)「70%の参考文献が3年以内でないと即リジェクト」: 確かにホットなトピックスに取り組んでいるように見えるので3年以内というのは非常に重要だと思います。しかし70%というのはどうでしょう。私は70%以下でしたがNature Communicationsに採択されました。今度、私がNature, Science本誌を書くときは70%にしようかなと思っています。
(5)「投稿した原稿がライバルの論文誌のフォーマットなら即リジェクト」: エディタは自分の論文誌が1番だと熱意を持って働いている人が多いです。あなたは本命でない、と言われて嬉しい人はいないですよね。
(6)「カバーレターの日付がずいぶん前だと即リジェクト」: カバーレターは原稿を率直にアピールする上で超超超重要です。こんな簡単なミスをするとはどうゆうことだとエディタは思うのでしょう。別の論文誌からリジェクトされた原稿をそのままこっちに持ってこられた気分になりますよね。リジェクトされたんだな、何がリジェクトされた理由だろうかという視点で見てしまうかもしれません。
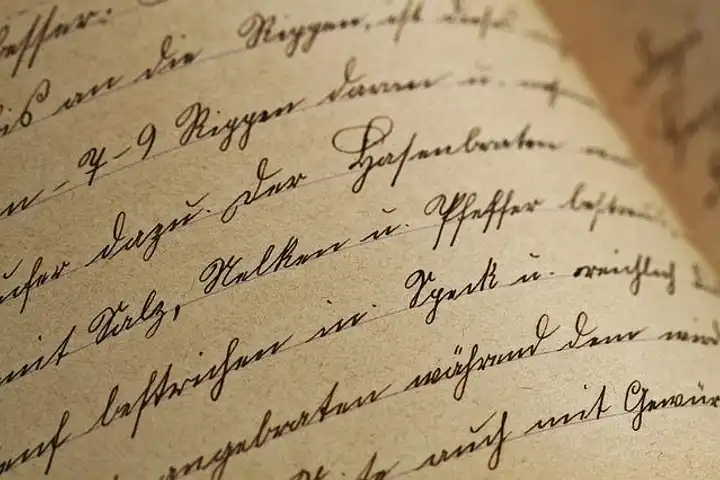
(7)「投稿する論文誌の論文をたくさん載せるとアクセプト率がアップ」: 確かにそうですね。エディターは論文誌のインパクトファクターをあげたいので、自分の論文誌を参照するのはエディターは喜ぶかもしれません。
(8)「3文に1個くらいのタイポがあると即リジェクト」: 英語が母語じゃない人にとって、とても厳しいなと思うのですが、NatureやLancetのエディターは1人のエディタが1日に200-400本の原稿を見なくてはいけないそうです。そんな極限状態を踏まえると、それくらいは当たり前かもしれませんね。
(9) 「英語は重要ではない。重要なのは原稿が持つメッセージだ」: え? なんか矛盾する意見を聞きましたよ。Nature Communicationsのエディタが言っていたのですが、彼女がイタリア人だったからかもしれません。逆に言うと、エディタによってばらつきがあるんだなと思いました。

どうですか!? 論文に関するオカルト、信じますか!? 書く能力のある人から聞いたアドバイスをまとめました。
レビューワ選びでズルするなとか、カバーレターをちゃんと書けとか、エディターレビューに関するオカルトばかりですよね。
レビューワレビューは、レビューの後にどうしてリジェクトされたのか説明があります。一方で、エディターキックは、どうしてリジェクトされたのか説明がないので、こうしたオカルトが大量に発生しているのだと思います。
まぁオカルトはほどほどにして良い論文とカバーレターを書く努力をしましょう。
これからも良い論文を書いていきましょう。
・Nature Communicationsに採択された原稿に、解説を付けたテンプレートを作りました。Webサイトの解説した内容が実際にどう論文に反映されたか実例を見ながら理解できます。研究者として上を目指したい方、ぜひ参考に。
論文の解説付きテンプレート、なぜ重要なのか?
・論文の書き方は教わりましたか? このWebサイトに書いてある高インパクト論文の書き方をスライドにして1つにまとめました。論文の "型" を自習する教材として最適です。ぜひ参考に。
高インパクト論文の書き方をどう自習するか? [結論:この解説付きスライドを読もう]