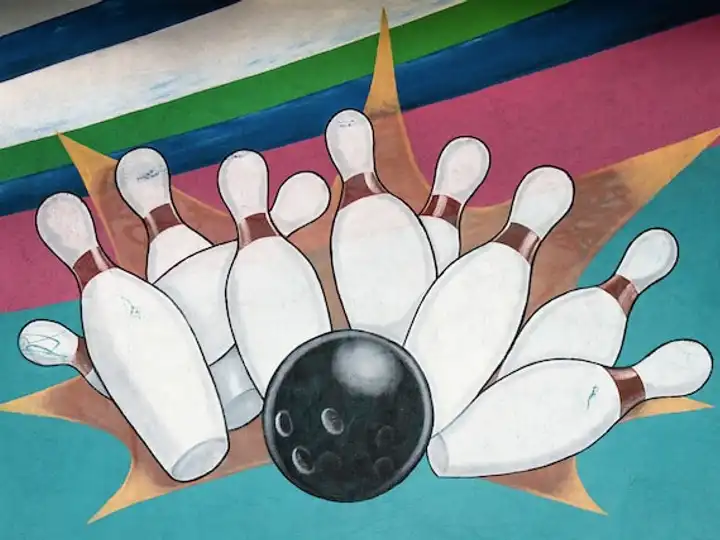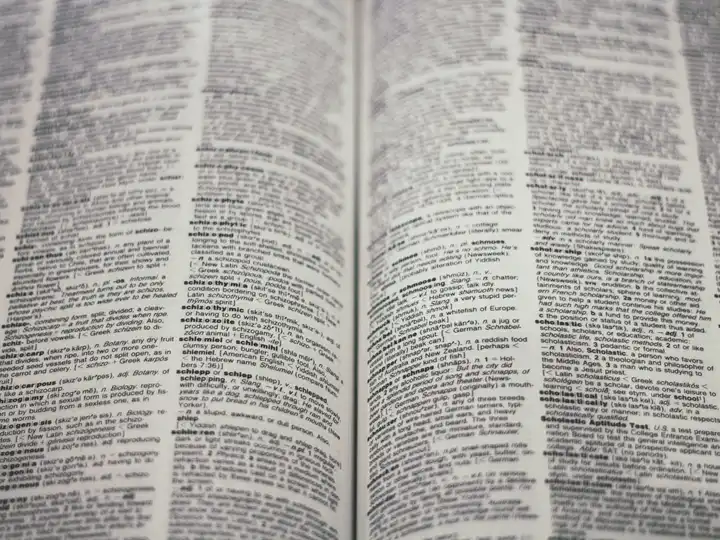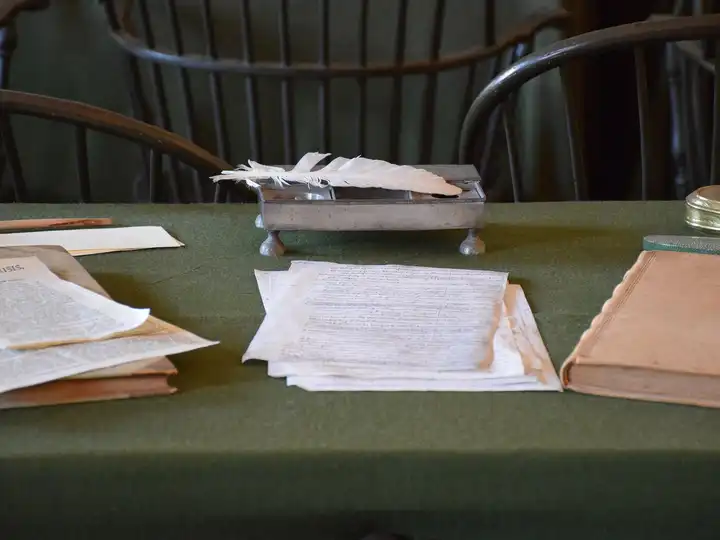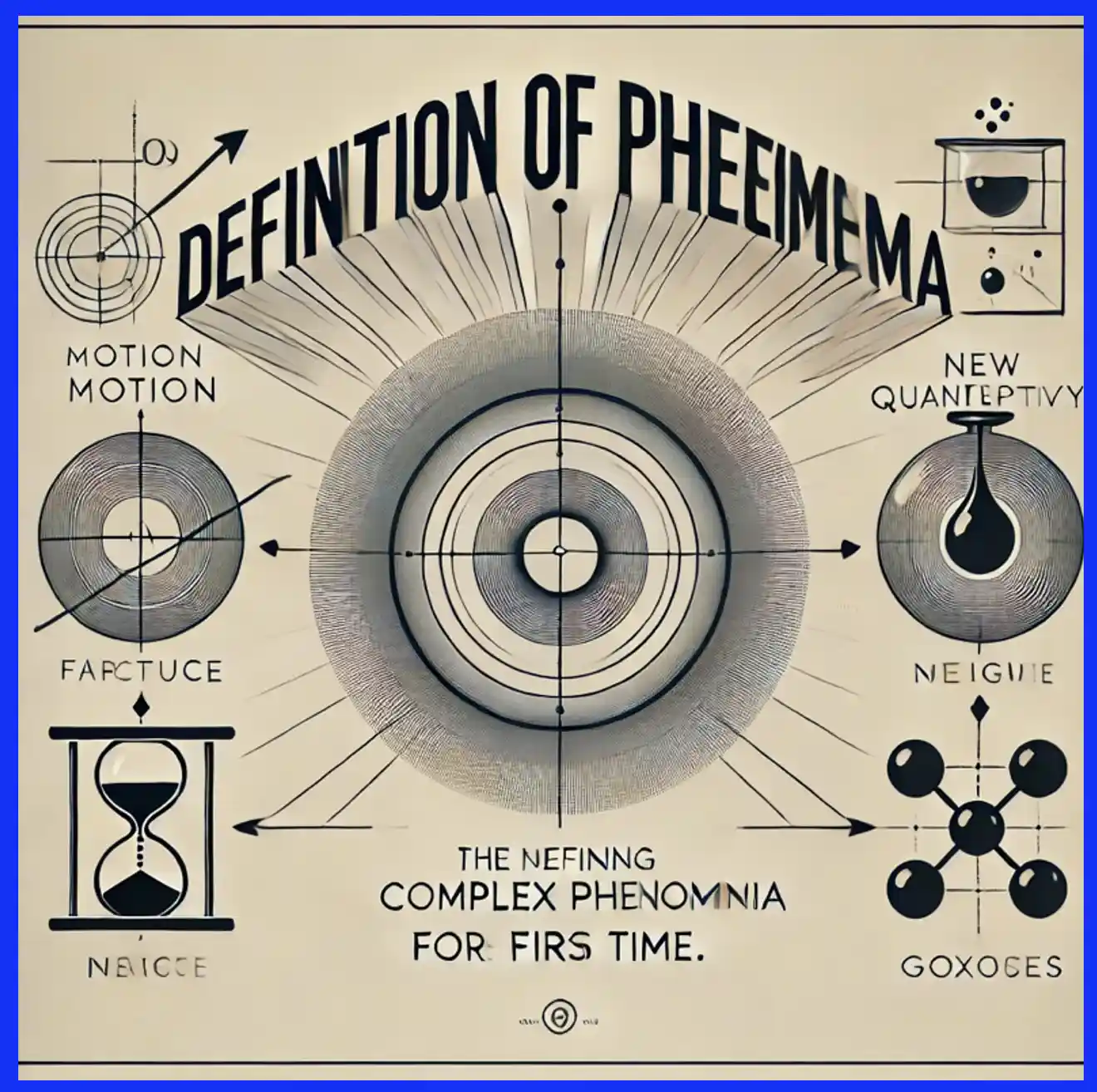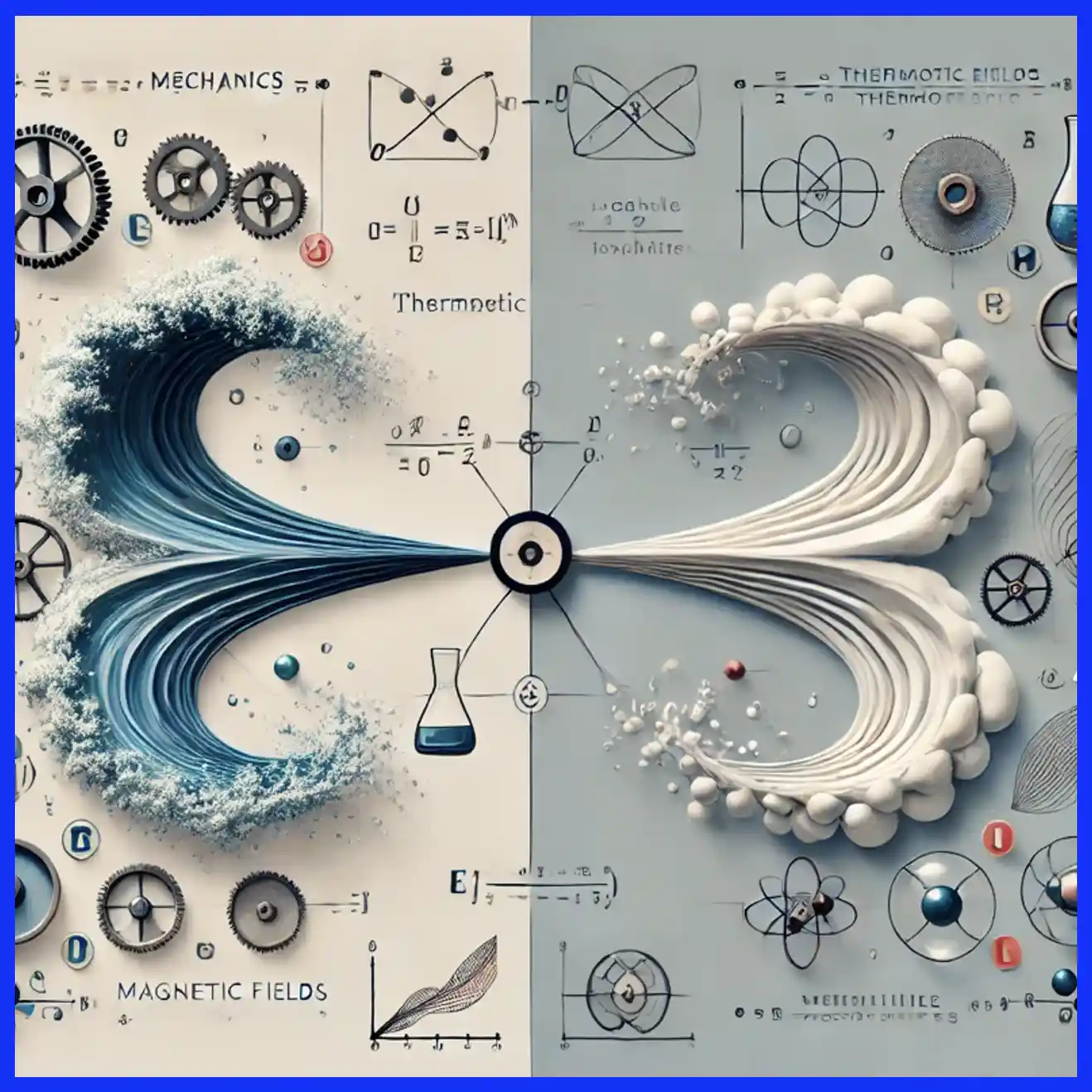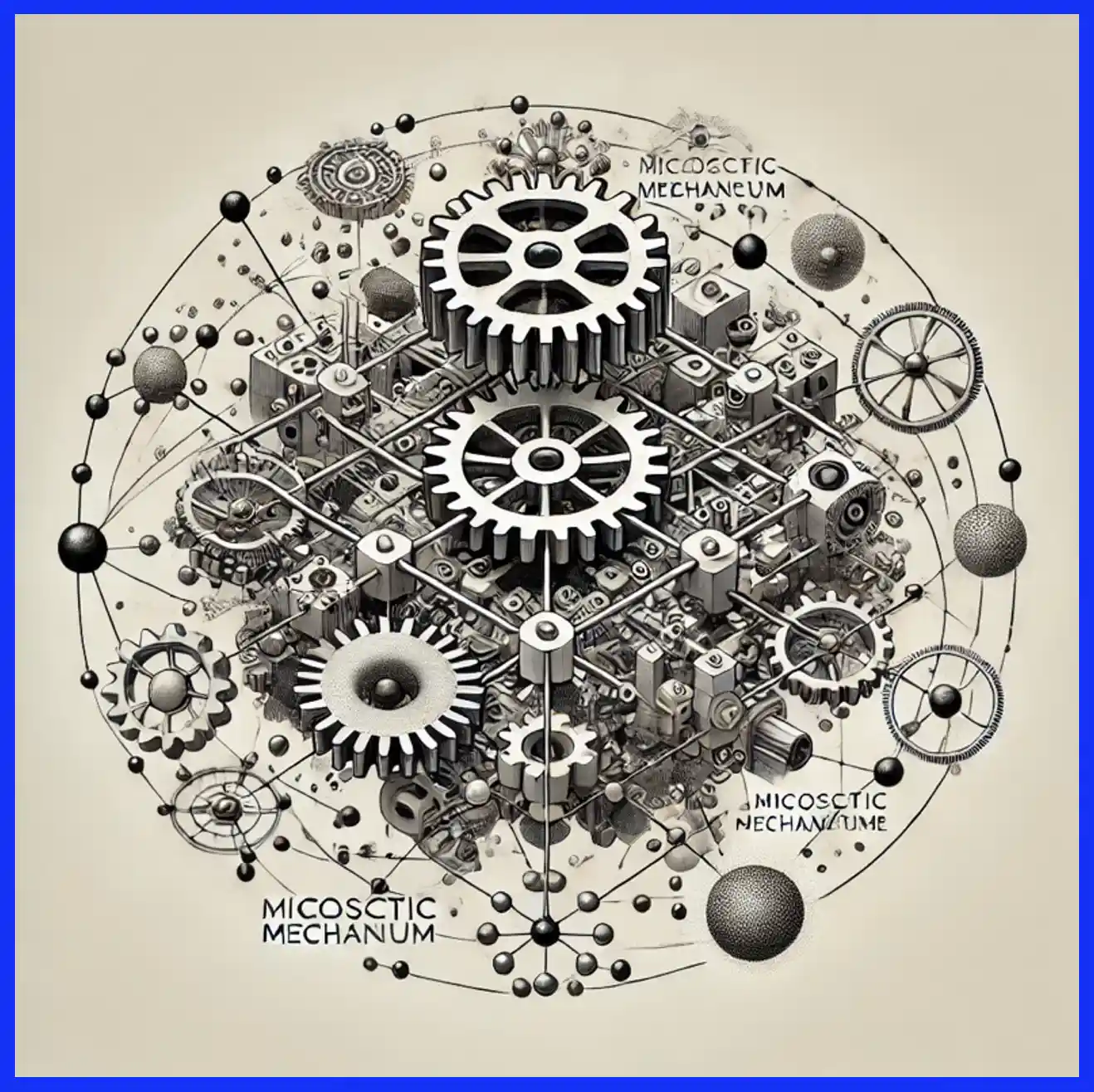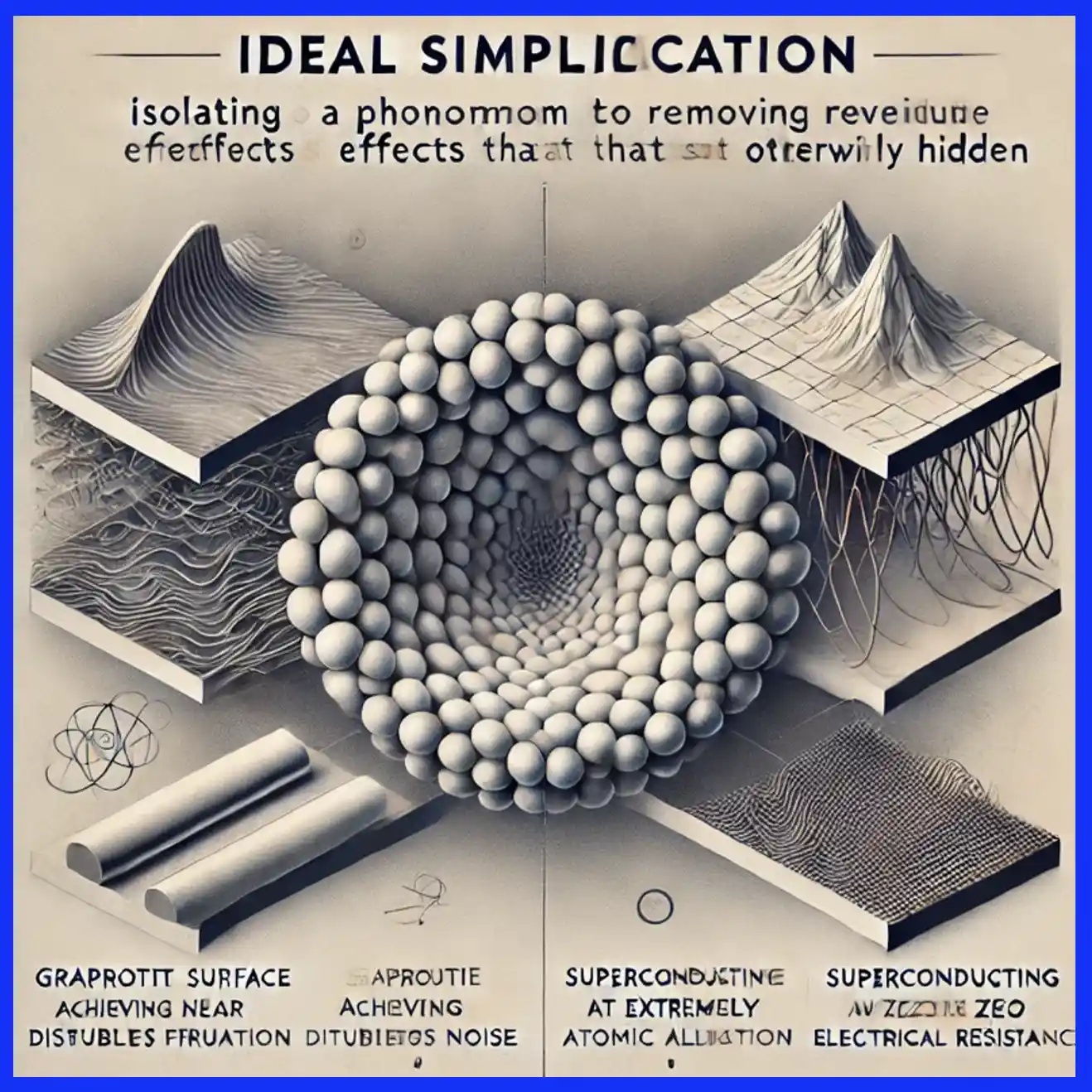まずインパクトとは何か?ということです。それは簡単です。「比較したら驚いた」これがインパクトです。
まず過去の結果と自分の結果とを比較し、違いがあれば自分の結果には新規性と独創性があると言えます。
そして、その新規性と独創性の中に予想できない "驚き" があれば、それがインパクトがです。新規性や独創性そのものに価値はありません。インパクトに価値があるのです。
「何をもって人は納得したと思うか」「どんな論理を話せば人は驚くのか」感情を動かす背景となる常識は、時代によって少しずつ変わっていくものです。しかし科学者を納得させる方法と、科学者を驚かせる方法に限って言うならば、ここ数百年単位で背景は大きく変化していません。これからも100年くらいはここで書かれているルールに大きな変化はないはずです。
「なるほど!」と強い納得感と驚きを生み出すインパクト(驚かせ方)には、基本的には4パターンしかないと私は思っています。この記事では、インパクトについて解説した後、最後にその具体的な4つの驚かせ方を要約して説明しました。