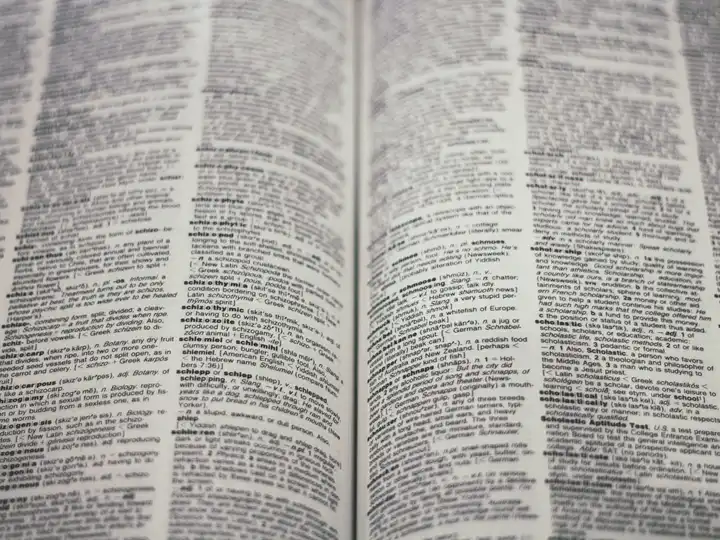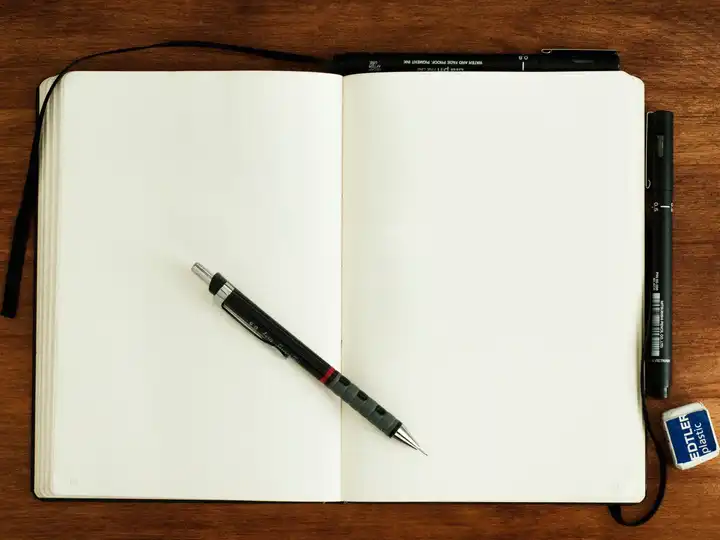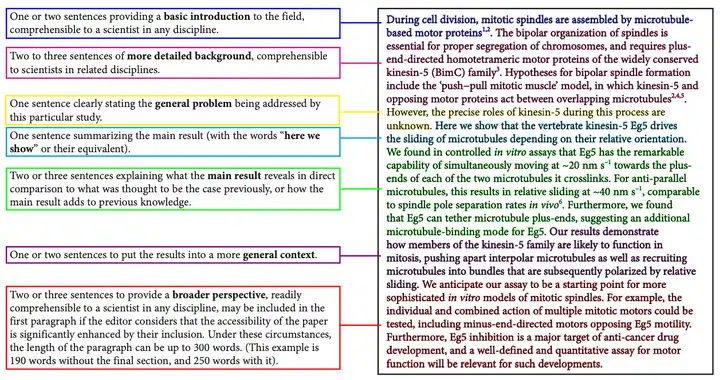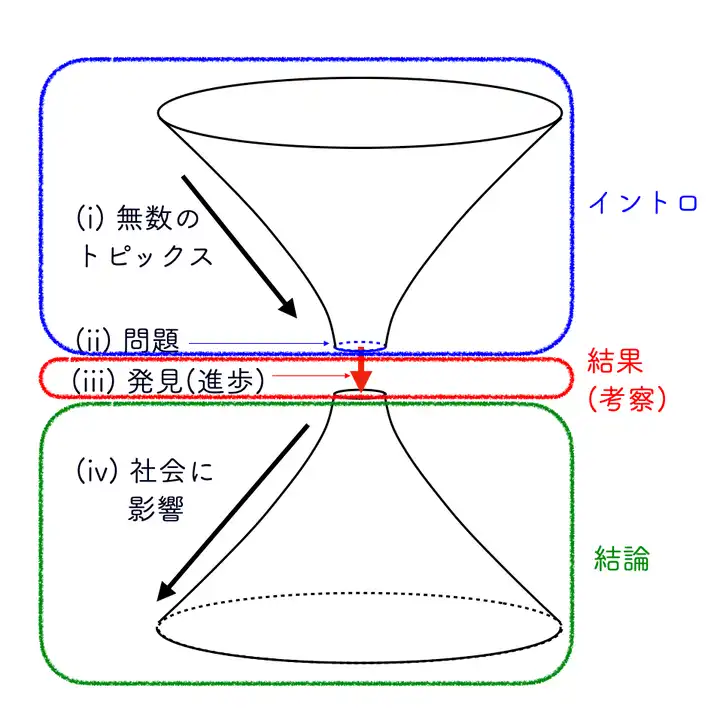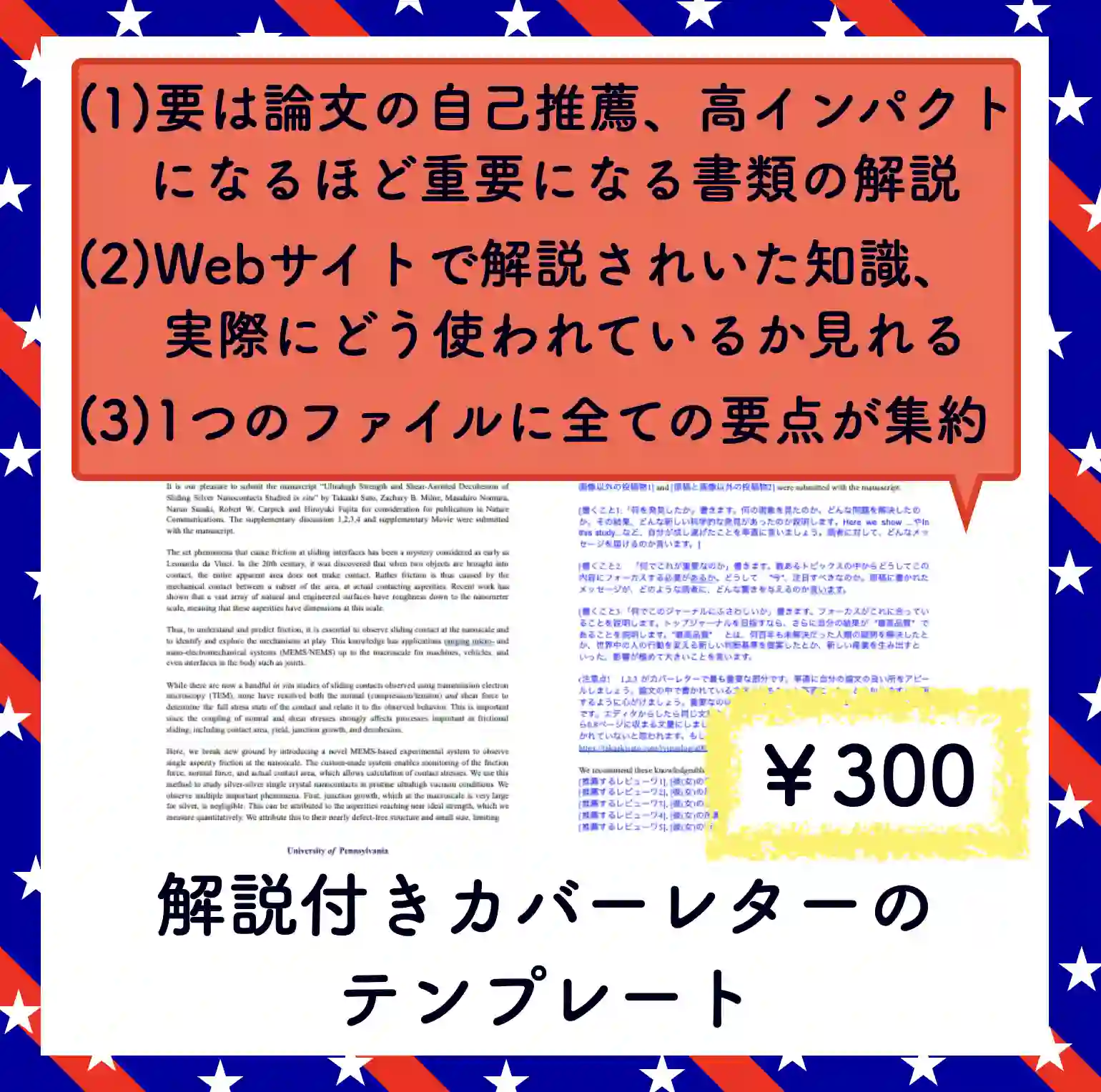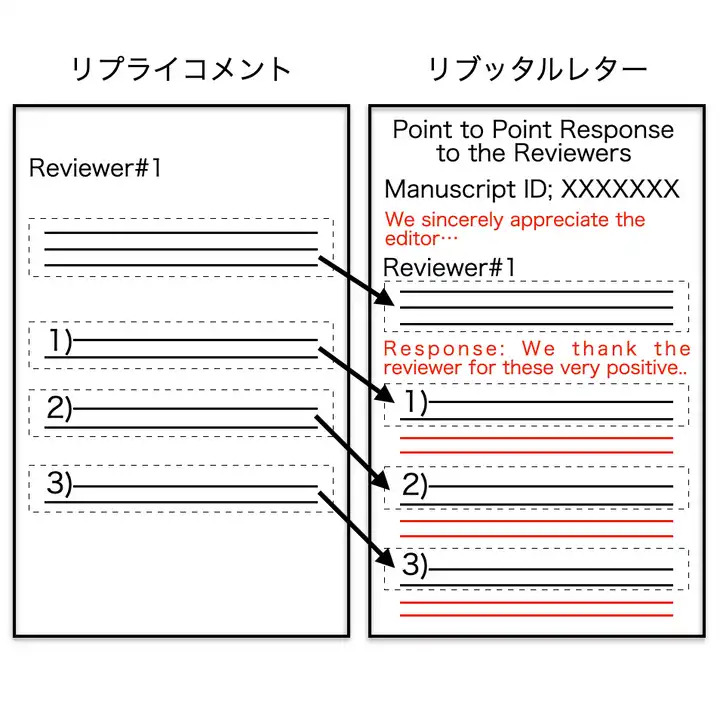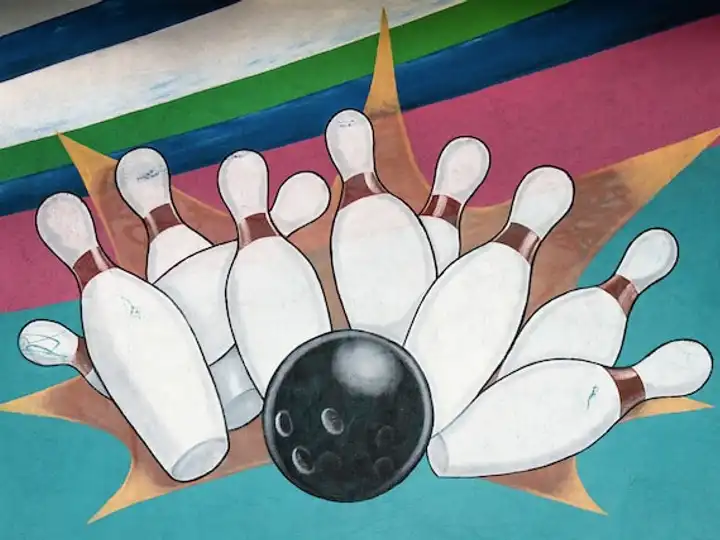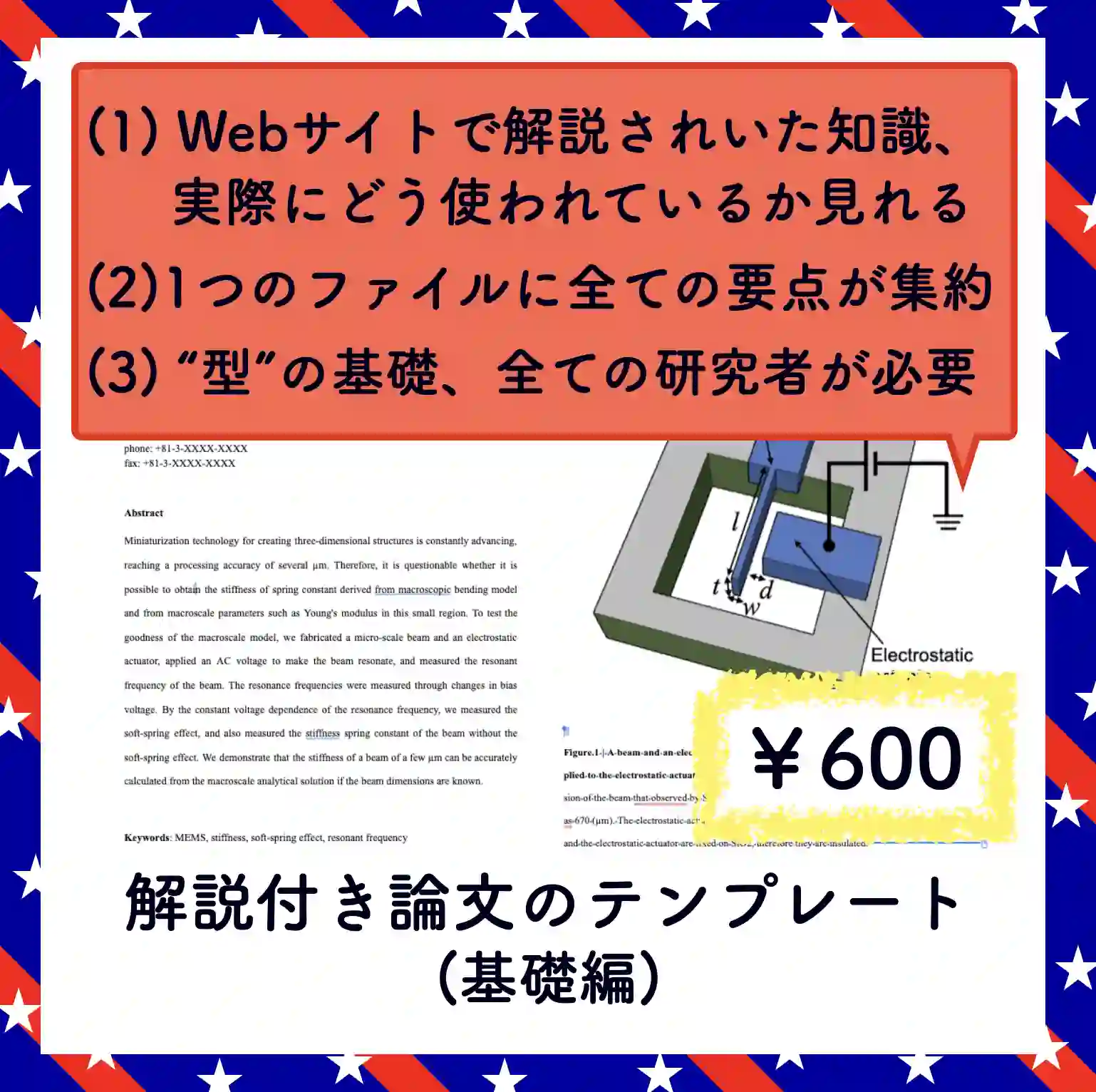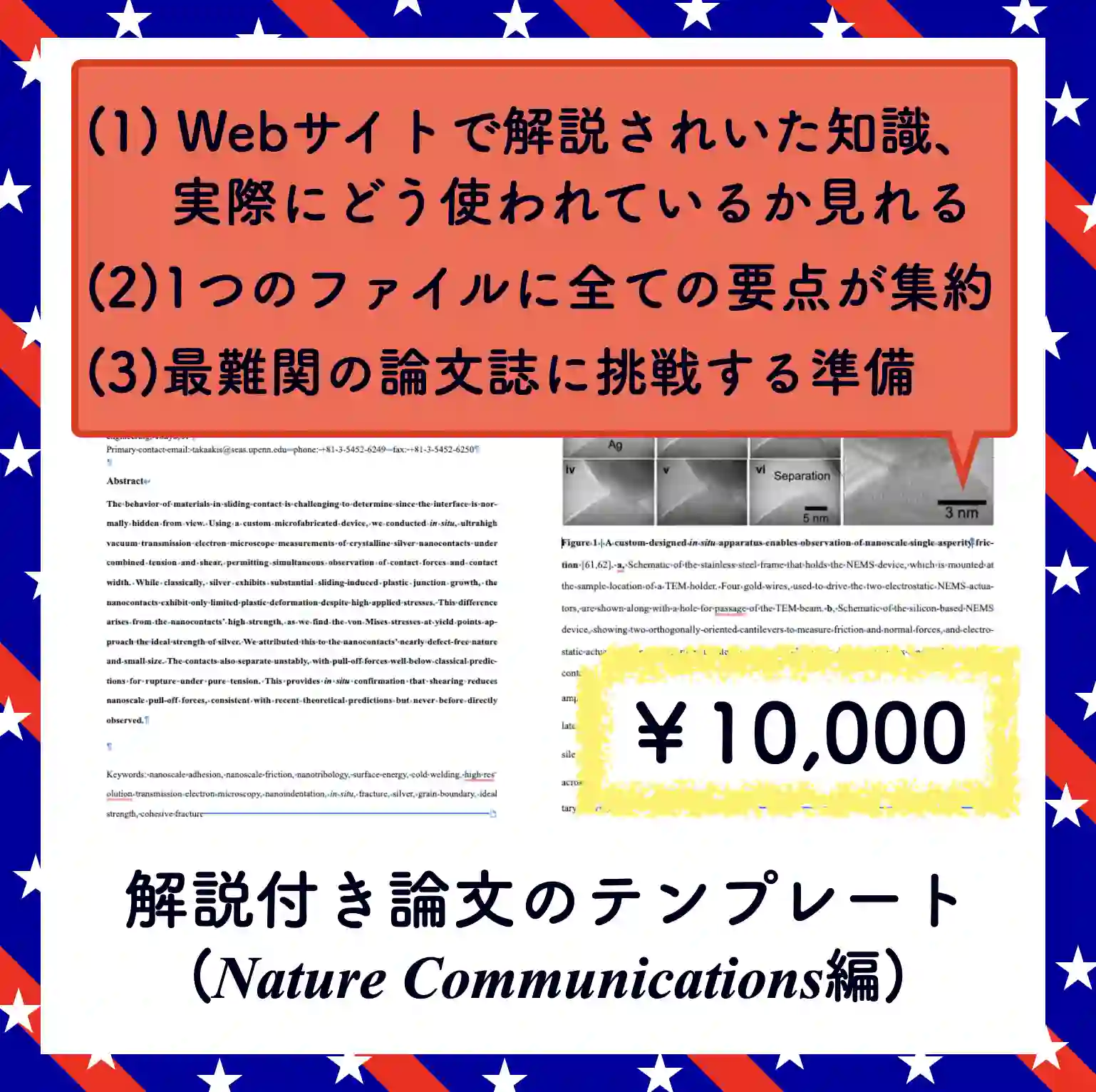結論では...
(1) 何をしたのか
(2) どんな傾向を得たか
(3) その傾向が, 過去の研究結果と比べて何が違うか?
(4) その違いが, 研究成果の流れを俯瞰的に見たときいに, どれだけ驚きなのか?
(5) 今後どんなことが起こりそうか?
(6) 今後どんな研究が必要かを書きます。
英語だとテンプレは...
- In summary, we AAAAAA..
- From this, we found BBBBBB exhibited multiple surprising and unique phenomena.
- First, CCCCCC.
- Second, DDDDDD.
- Third, EEEEEE.
- FFFFFF.
- GGGGGG is a complex phenomenon involving HHHHHH....
A,B,C,D,E,F,Gを自分の内容に書き換えるだけです。
結論をアブストの内容をコピペしないで下さい。アブストは、論文の内容を簡潔にまとめた文です。一方で、結論は得られた結果が何を意味するのか考察する部分であって、決して「まとめ」を書く部分ではありません。気をつけて下さい。
高インパクト論文の結論の書き方の詳細をもっと勉強したい方、この記事を見た下さい。
論文の結論の書き方: Nature, Science, Cellへの道