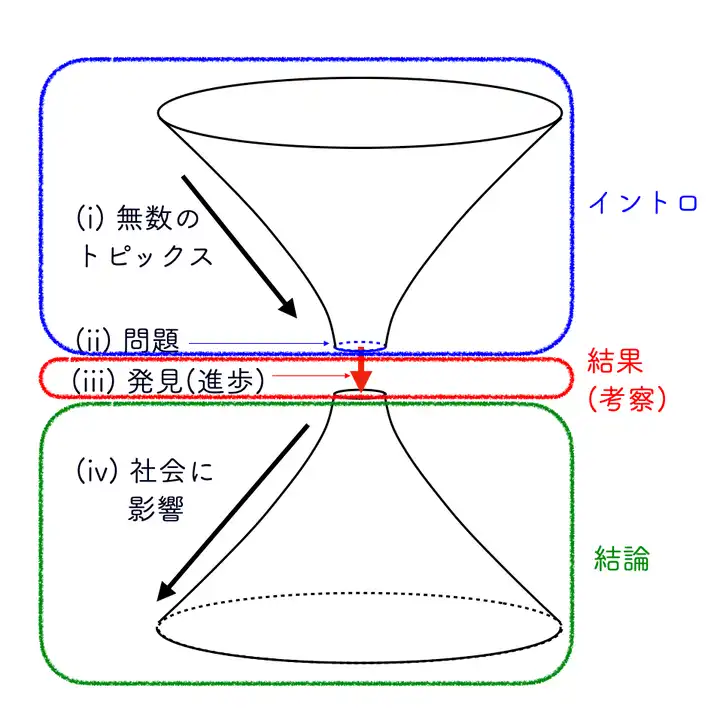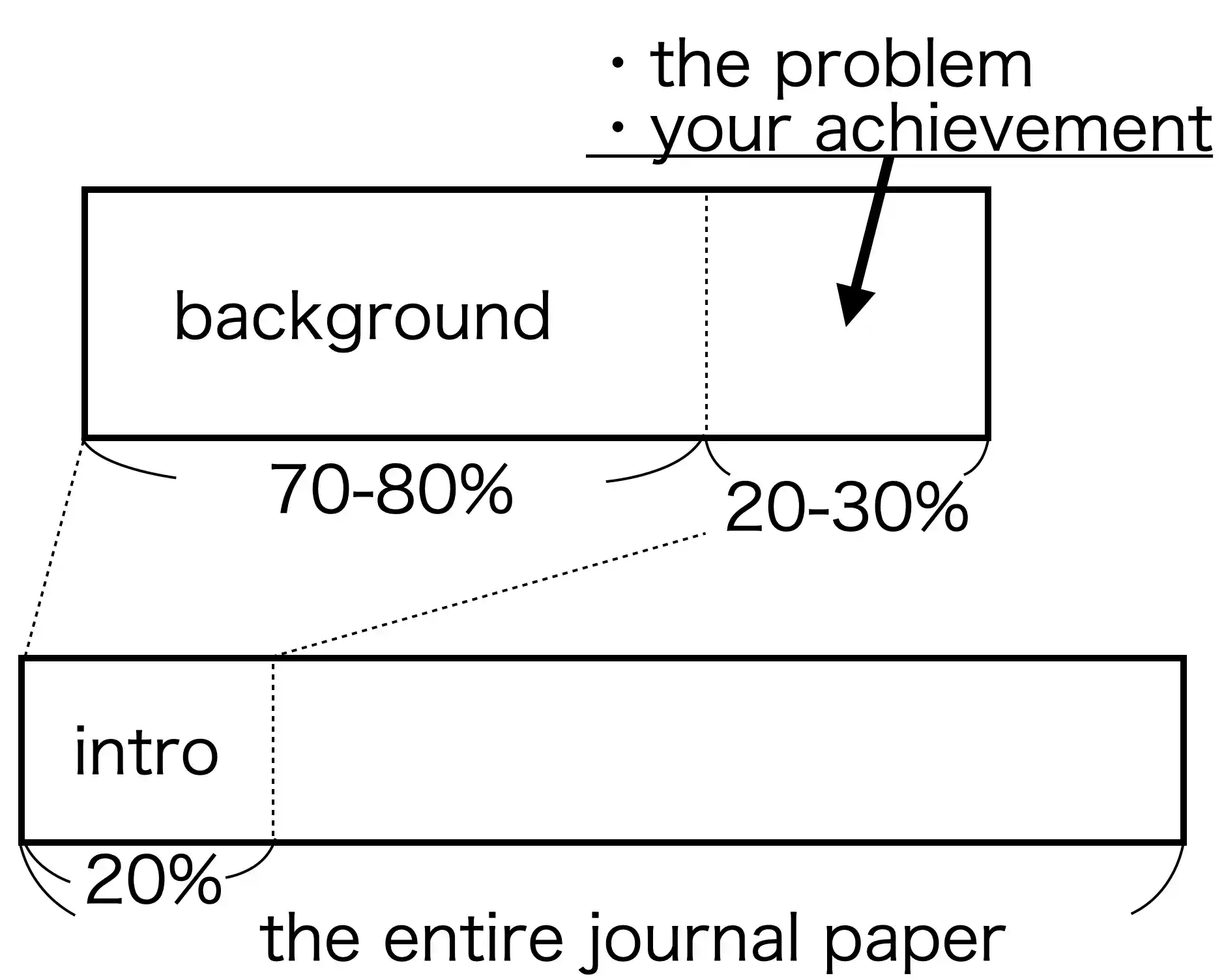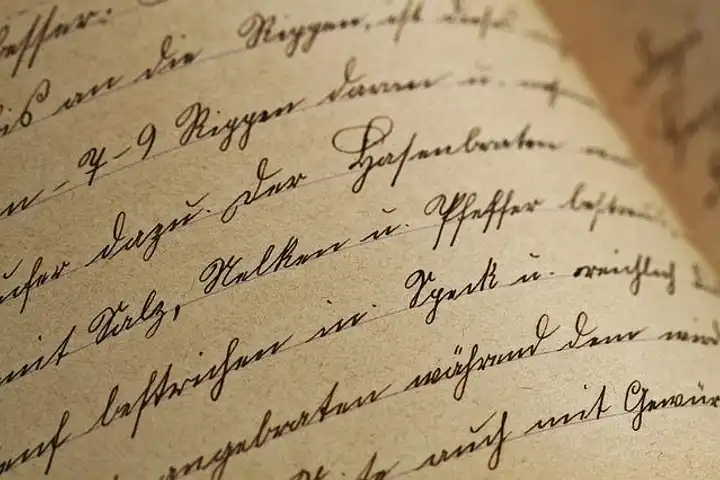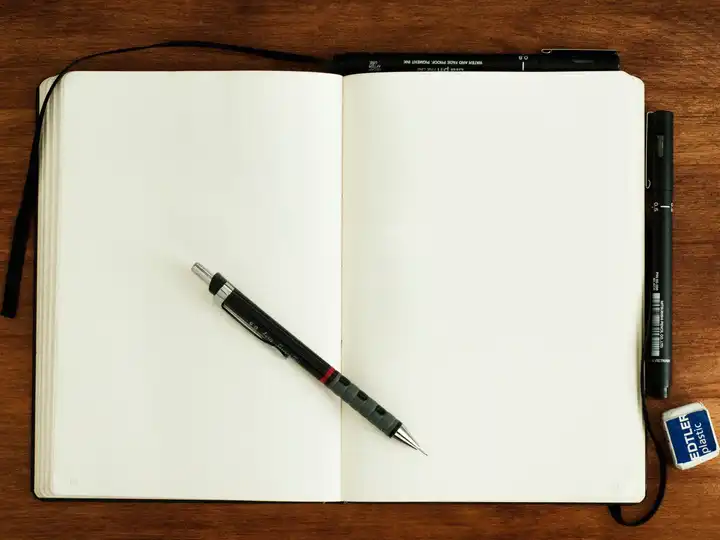以上のコツが守られていても、頻発する誤りも紹介しておきます。私が強くオススメするのは、Howeverの文の直後にIn this study, weの文を持ってくることです。つまり、「However, (研究の問題点). In this study, we (私たちがやったこと).」と間に別の文章を置かずに書くのを強くオススメします。
問題点に対して他の研究者が過去に様々なアプローチで研究してきたはずで、自分だけがこの問題に取り組んできたわけではないはずです。なので時系列順に研究を紹介しようとすると、Howeverの文とIn this study, weの文の間に、過去の研究の内容を紹介したくなってしまいます。
しかしこれはやめましょう。"時系列順" より "論理の明快さ" を優先させましょう。2つのパターンを見せるので、どちらの方が読みやすいか比較してみて下さい。
パターン1「XXXXXX. However, 原子レベルの直接観察ができていないため直接の原因を掴めていない問題がある. この問題に対して今までピエゾアクチュエータによる実験がなされ[1]、また熱膨張アクチュエータによっても観察が試みられた[2]。しかし、原理的に避けられないノイズのせいで現在まで原子レベルの観察には至っていない。In this study, 我々はマイクロマシンを用いて原子レベルの観察を成功させた。 The result shows that XXXXXXXX.」
パターン2「XXXXXX. However, 原子レベルの直接観察ができていないため直接の原因を掴めていない問題がある. In this study, 我々はマイクロマシンを用いることで原子レベルの観察を成功させた。この独自の技術によって、ピエゾアクチュエータ[1]や熱膨張アクチュエータ[2]では原理的に避けられないノイズを抑えられた。The result shows that XXXXXXXX.」
一目瞭然ですよね。しかも実際の論文だと単語が難しくなり、文も長くなるのでHoweverとIn this studyの間隔はもっと長く感じるはずです。Howeverの文の直後の文にIn this study, weの文をがんばって持ってきましょう。