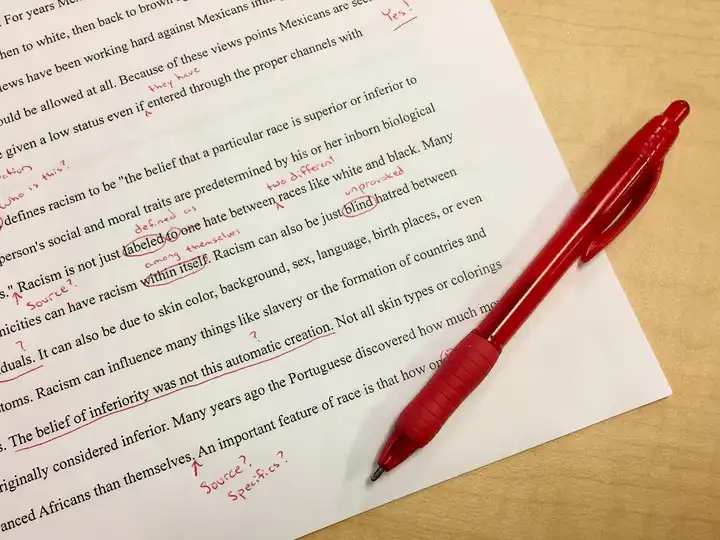私がNatureのエディタに話した時、「論文の最後にまとめは書かなくていいと思う」と言っていました。同じ文をもう一度書く必要がないそうです。論文の情報の密度を上げたいのでしょう。現代の論文において結論はまとめであってはならないのです。
結論では書くべきことは以下の6点。
(1) この研究で何をしたのか
(やったことを2-4文で説明する)
(2) どんな傾向を得たか
(結果の特徴を端的に紹介)
(3) その傾向が, 過去の研究結果と比べて何が違うか?
(できれば定量的に違いを説明する)
(4) その違いが, 研究成果の流れを俯瞰的に見たときいに, どれだけ驚きなのか?
(個々の違いを見るのではなく複数の研究結果の流れを見て、自分の結果がどの流れに属しているか、どの流れを否定するかなど、より俯瞰的に見たときの今回の結果の意味を客観的に説明する)
(5) 今後どんなことが起こりそうか?
(この結果を知らないと将来どんなことが起きそうか紹介する)
(6) 今後どんな研究が必要か
(1文くらいで書く)
もし得られた傾向が1つなら、(1)(2)(3)(4)(5)(6)で書きます。もしもし得られた傾向が2つなら、(1)(2)(3)(2')(3')(4)(5)(6)と得られた傾向ごとに書く内容が増やします。ちなみにもし得られた傾向が3つなら、(1)(2)(3)(2')(3')(2")(3")(4)(5)(6)です。
具体的には以下のように書くのを提案します。