広辞苑によれば論文とは…
「論議する文。理義を論じきわめる文。論策を記した文」だそうです。
Wikipediaによれば論文とは…
「学問の研究成果などのあるテーマについて論理的な手法で書き記した文章」だそうです。
端的に説明できていると思いますが、正確ではありません。この記事では、論文で書かれるべき内容について紹介します。
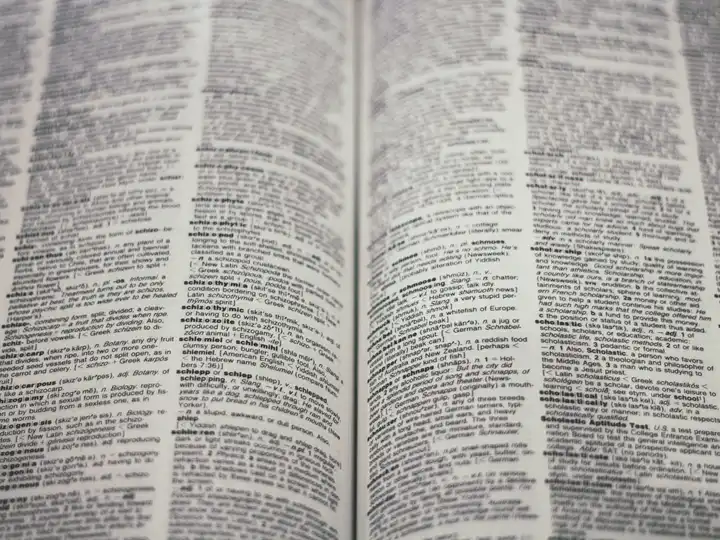
(1)論文には何が書かれているべきかや、(2)エッセイやレポートと何が違うのかを知りたいですか?
この記事では、具体的な違いと、論文にはどのような内容を含まねばならないのか紹介しました。
これから論文を書く人、そもそも論文って何だろうか知りたい人は必読です。
ちなみに、この記事は「論文の内容」だけにフォーカスした記事です。論文誌に掲載されないと論文とは言えませんし、そのためには論文誌の査読を合格しなくてはいけません。こうした「論文誌」や「査読」を含めた「論文の定義」を網羅的に知りたい人は、まとめ記事 [論文とは何? 論文誌って? 査読って? 論文に関する疑問に答えます!]を参考にしてください。
「論議する文。理義を論じきわめる文。論策を記した文」だそうです。
「学問の研究成果などのあるテーマについて論理的な手法で書き記した文章」だそうです。
端的に説明できていると思いますが、正確ではありません。この記事では、論文で書かれるべき内容について紹介します。
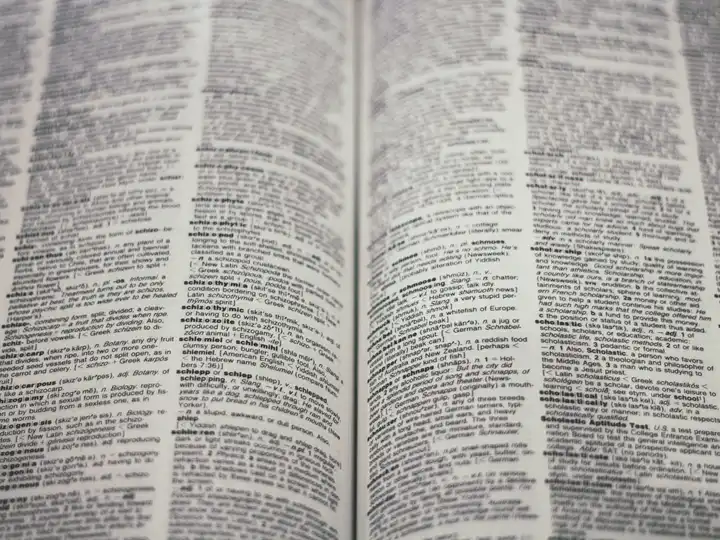
論文と、エッセイや詩とは違いは「客観的なデータに基づいて考察している」がどうかです。エッセイや詩は自分が感じたことや、感想を書いても問題ありません。つまりエッセイや詩は、主観的な内容が含まれています。
例えば、「駅前の賑わいから考えるに、災害からの復興は始まっており、今後の経済の発展が期待できる」という文章はどう思いますか?これはエッセイの文章です。なぜなら賑わっているかは著者の主観であるため、それから導かれた「復興が始まっている」と「経済の発展が期待できる」という結論は共に主観的な情報になるからです。論文にこうした主観的な考察を記載してはいけません。
「復興が始まっている」と言いたいなら、地域に住んでいる人数の増加量であったり、家屋の数の増加量を記載する必要があります。「経済の発展が期待できる」と言いたいなら、取引の金額の増加量や雇用数の増加量を記載しなくてはいけません。すなわち論文とは、客観的な事実である“データ”から導かれた考察によって構成されていなくてはいけません。
さらに、論理の飛躍があってもいけません。例えば「風が吹けば桶屋が儲かる」はダメです。論文では以下のような言い方になります。「風が吹くと砂の粉塵が舞い、それが目に入って盲目になる人が増える。盲目の人の有力な仕事は三味線引きなので、三味線の材料として猫の皮が使われるため猫が少なくなる。すると猫の天敵であるネズミが増えて、ネズミが風呂の桶を噛んでダメにしてしまう。ゆえに風が吹けば桶が少なくなって、桶屋が儲かると考えられる」と言いましょう。このように論文において、データと結論を導く考察の過程で、論理の間に飛躍があってはいけません。

論文と、新聞記事との違いは「根拠の妥当性を確認できる」です。例え客観的な事実に基づいて記事を書いても、それだけでは論文とは言えません。論文とは、根拠にしたデータの妥当性を読者が確認できる原稿です。新聞記事は客観的証拠から初めて結論を主張します。しかしその根拠をどうすれば得られるのかは説明していません。このため、新聞記事に信憑性があるのかは誰も確認できず、結論が妥当かは新聞社のモラルを信頼するしかありません。
論文には、根拠となるデータの妥当性を読者が確認できるようにするために、根拠となるデータの取得方法やデータの計算方法も記載してあります。さらに誰に聞けば再現するための実験の詳細を教えてくれるかも記載してあります。
ちなみに、読者がデータの信憑性を確認できるとゆうのは、大前提としてそのデータに再現性がある必要があるということです。再現性とは、同じ条件で実験(もしくは計算)すれば、世界中の誰でも同じ(ような)データを得られるということです。つまり、1度きりで誰も再現できない根拠から導かれた結論が書かれている原稿は、論文にはなりません。
このように論文には、根拠となるデータの信憑性を読者が自分で確認できます。論文と新聞記事との違いは、結論の根拠となるデータの妥当性を自分で確認したいと考えたとき、その実験を再現してデータを取得する方法が記されているかどうかです。
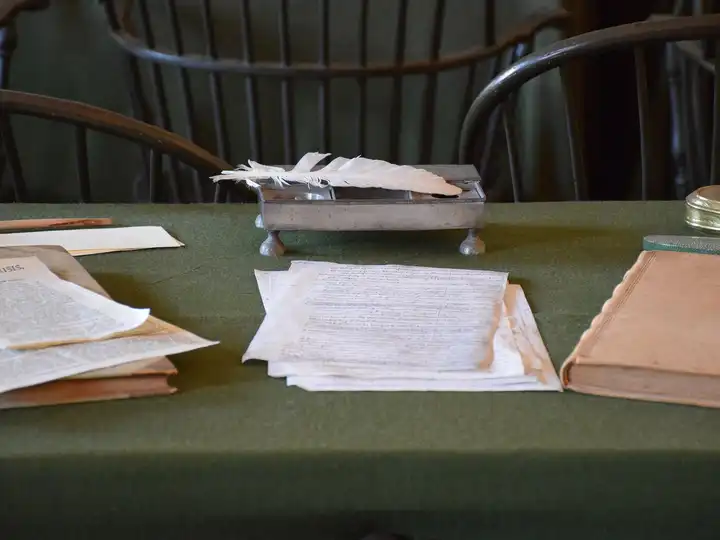
論文と、実験レポートとの違いは「新規性」があるかです。実験レポートは、根拠となる客観的なデータに基づいて考察し、さらにその実験や計算がどのように行われたのか記載してあります。しかしそれだけでは論文とは言えません。論文には、今まで他の論文で考察されてこなかった何か新しい発見が含まれていないといけません。実験レポートは、すでに無数の学生が同様の内容を書いているため新しい発見がないので論文とは言えないのです。
新規性とは具体的に何かというと、過去の論文と比較して自分の結果と何が違うかです。過去に出されてきた自分の結果に関係ある論文を読んで、自分の結果に差分があればそれが新しいということです。逆を言うと、過去の論文と自分の結果とを比較していない原稿は論文ではありません。
NatureやScienceといった名誉ある論文誌に採択される論文は、新規性の中に「驚き」が含まれていなければなりません。ただ単に新しければそれでいいのではなく、(1)今まさに注目すべきホットな内容であるとか、(2)何百年も解かれなかった問題がついに解けたとか、(3)新しい産業が始まると言った、波及効果の大きい新規性が好まれます。
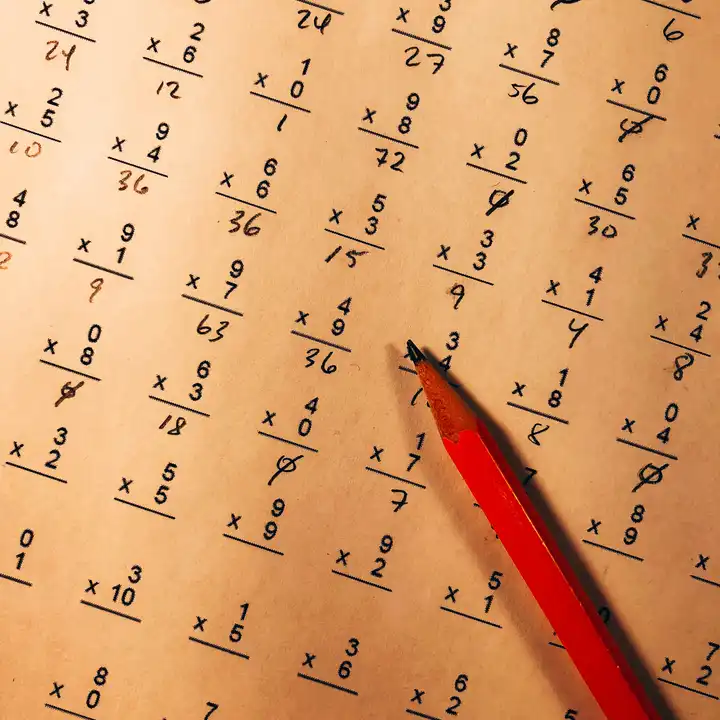
このように論文とは...
(1)主観的な根拠に基づいて考察せず、客観的なデータに基づいて考察された原稿です。
(2)また、根拠となるデータの信憑性を読者が自分で確認できます。つまり結論の根拠となるデータの妥当性を自分で確認したいと考えたとき、その実験を再現してデータを取得する方法が記されています。
(3)最後に、論文は新規の内容でなくてはいけません。つまり、今まで他の論文で考察されてこなかった何か新しい発見が含まれていないといけません。
これらの条件を満たしている原稿を、論文誌に投稿して、論文誌が掲載した原稿を論文と呼びます
・原稿が完成したらこれを論文誌に投稿します。論文誌に採択されて正式に論文と呼ばれるわけです。次のステップである「論文誌」について説明したので、興味のある方、この記事を参考にしてください。
論文誌とは何か説明しました。論文とは、論文誌に掲載された原稿です
・Nature Communicationsに採択された原稿に、解説を付けたテンプレートを作りました。Webサイトの解説した内容が実際にどう論文に反映されたか実例を見ながら理解できます。研究者として上を目指したい方、ぜひ参考に。
論文の解説付きテンプレート、なぜ重要なのか?
・論文の書き方は教わりましたか? このWebサイトに書いてある高インパクト論文の書き方をスライドにして1つにまとめました。論文の "型" を自習する教材として最適です。ぜひ参考に。
高インパクト論文の書き方をどう自習するか? [結論:この解説付きスライドを読もう]