インパクトファクターとは、その論文誌の論文の引用数の平均値です。要は、インパクトファクターが高ければ、引用数の平均値が多いということです。
論文誌ごとにインパクトファクターは異なります。
インパクトファクターが高い論文誌の方が、難易度が高い傾向があります。
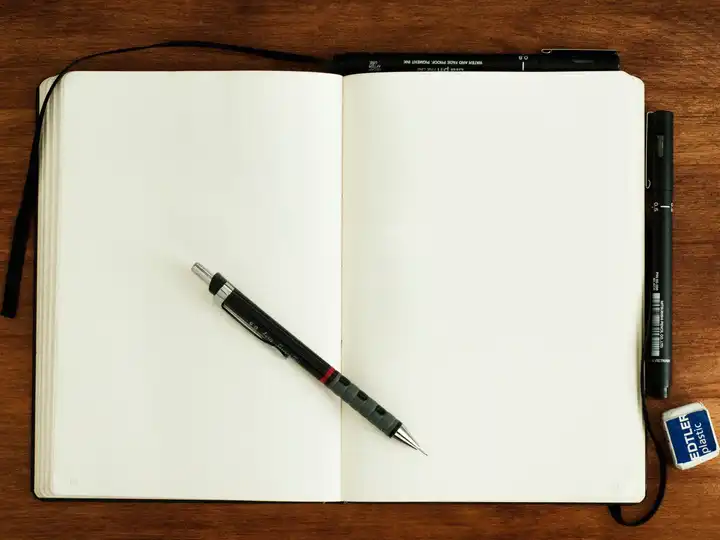
論文誌の価値の指標となるインパクトファクターを知りたいですか? 有名な論文誌の値を掲載しました。
また、インパクトファクターの計算方法も説明しました。
論文を書く方、まず知っておいて欲しい基礎知識です!
ちなみに、論文とは何か? 論文誌とは何か? 査読とは何か? といった基礎を網羅的に知りたい方は、[この記事]を参考にしてもらいたいです
The Lancet: 168.9
Nature: 49.96
Science: 47.27
Nature Materials: 43.84
Cell: 41.58
Nature Nanotechnology: 39.21
Nature Communications: 17.69
ACS Nano: 15.88
Small: 13.28
Nano Letters: 11.19
Carbon: 9.59
Physical Review Letters: 9.16
Physical Review B: 4.04
Applied Physics Letter: 3.97
Nanotechnology: 3.87
Tribology Letters: 3.11
Japanese Journal of Applied Physics: 1.36
インパクトファクターとは、その論文誌の論文の引用数の平均値です。要は、インパクトファクターが高ければ、引用数の平均値が多いということです。
論文誌ごとにインパクトファクターは異なります。
インパクトファクターが高い論文誌の方が、難易度が高い傾向があります。
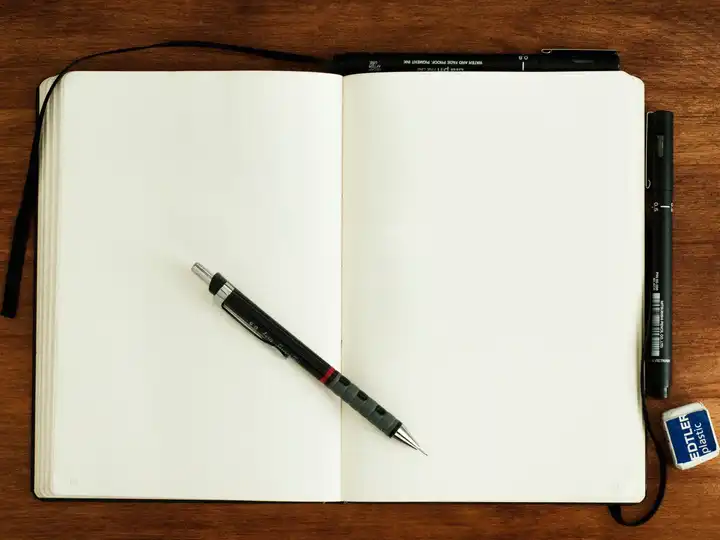
具体的にいくつの数字からが高インパクトファクターかは、研究分野によって大きく異なります。
私の分野(物理, ナノテク, 材料)では...
・3未満だと低インパクトファクター
・10以上で高インパクトファクター
・Natureシリーズ,Scienceシリーズ,Cellはさらにその上のランク
だと思います。
論文を大量に引用しないでも自分の論文を書ける数学などの分野では、論文誌のインパクトファクターは低くなる傾向があります。一方で、医療のように多くの技術を使って論文を書く必要がある分野のインパクトファクターは高くなる傾向があります。このため分野を横断してインパクトファクターを比較してはいけません。

私はいい結果がでたら、高いインパクトファクターを目指します。これくらいの姿勢がオススメです。他人にマウントを取るために、より高インパクトにチャレンジするのではありません。過去の自分を超えるために高インパクトの論文誌を目指すのです。
インパクトファクターなんて関係ない、論文の「数」が重要だと堂々と言う先生がけっこう多いです。けれどもインパクトファクターが低い論文誌だと、査読者から「何が独創的なのか」「ここの論理に飛躍がある」といった指摘ばかりになり、「発見の科学的な価値」をほとんど議論しません。
こうした「自分がやった事を報告し続ける作業」はとても辛く、長い目で見ると疲弊するだけです。高インパクトのジャーナルに自分の成果が掲載された時の、圧倒的な達成感、強烈な自己肯定感、何物にも変えられない幸福感、ぜひ体験してもらいたいです。
科学者としてインパクトファクターを意識しない姿勢って、そんなにカッコいいでしょうか? 私は、上を目指す姿勢を応援します。頑張って高いインパクトファクターの論文誌に論文を書きましょう! このサイトはそれを全力でお助けします。

インパクトファクター以外の論文誌の指標が現れてきました。インパクトファクターの値は論文誌からかなり操作できる問題があります。例えば、レビューペーパーをたくさん掲載すればciteされる数が増えるので、論文誌のインパクトファクターを引き上げることができます。他にも、計測手法や計算方法を記載した原稿も参照されやすいため、こうした原稿を積極的に編集者が掲載することでインパクトファクターをつりあげるテクニックはよく知られています。
また、Nature論文からciteされた数と、学生でも簡単に採択される論文誌から採択された数が、同じ価値でいいのでしょうか? インパクトファクターにはこうした問題が含まれています。
そこで、インパクトファクターの他にもCite Score, SJR, Eigenfactor Score, SNIPといった値が現れました。これらはgoogleの検索システムのように、単純な参照数だけで価値を計算するのではなく、どの論文誌から参照されたのかといった参照先に重みづけした論文誌の計算方法です。
注意しなくてはいけないのは、それぞれの値の計算方法が全く分からないので、何の価値を見ているのか分からない欠点があります。

・Nature論文とそうでない論文は、投稿してから採択されるまでのプロセスが結構異なります。詳しく知りたい方、こちらを参考に。
Nature論文とそうでない論文、採択まで何が違う?
・Nature Communicationsに採択された原稿に、解説を付けたテンプレートを作りました。Webサイトの解説した内容が実際にどう論文に反映されたか実例を見ながら理解できます。研究者として上を目指したい方、ぜひ参考に。
論文の解説付きテンプレート、なぜ重要なのか?
・論文の書き方は教わりましたか? このWebサイトに書いてある高インパクト論文の書き方をスライドにして1つにまとめました。論文の "型" を自習する教材として最適です。ぜひ参考に。
高インパクト論文の書き方をどう自習するか? [結論:この解説付きスライドを読もう]