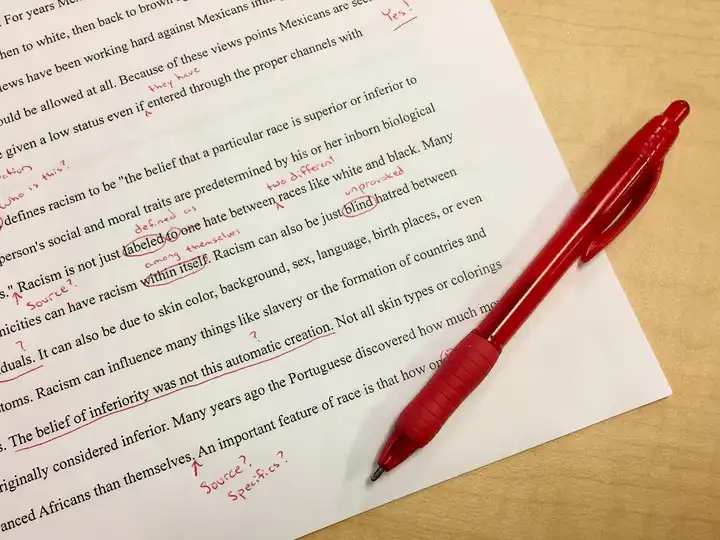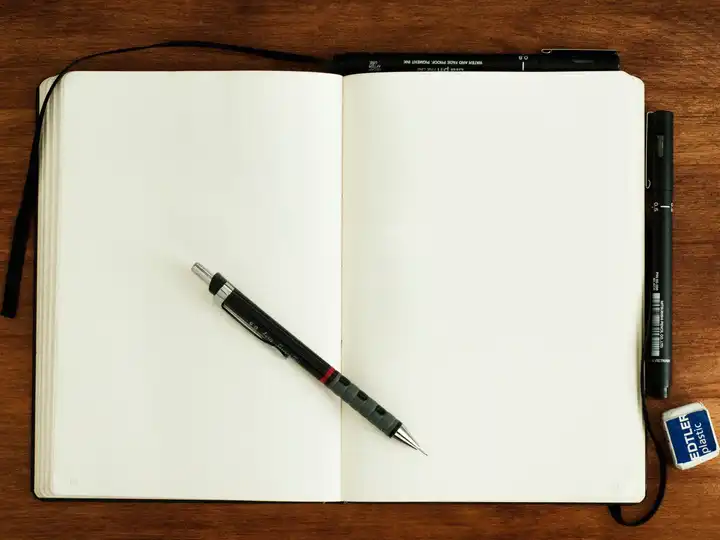Nature系の論文誌の査読者と、そうでない論文誌の査読者は、研究者としてのランクが全然違います。
低インパクトの論文誌の査読者はランクが低いとは言いません。しかし、トップジャーナルに掲載されたことがない研究者が、低インパクトファクターの論文誌では査読者としてあなたの原稿の査読に参加する可能性があります。
これは私の経験から導かれた主観ですけど、トップジャーナルに掲載させた経験がない研究者は、「科学の進歩とは何か (つまりインパクトとは何か)」を理解していない研究者が多いです。("インパクト"について知りたい方は、この記事を見て下さい)
Nature論文を書くために必須,「インパクト」の作り方!
その結果、(a)この文章の論理が通っていないとか、(b)この解析手法を使うべきではないとか、(c)この説明が不十分だとか、(d)何がオリジナルなのかといった、論文の詳細のあげ足を取るような指摘ばかりになる傾向があります。
低インパクトの論文誌では、科学の進歩(=インパクト)について議論されることは少なく、(a)-(d)のような不毛な争いに巻き込まれがちです。
(a)-(d)も重要なことではありますが、不毛な争いに巻き込まれない技術を身につけても、その技術はトップジャーナルの掲載にはほとんど活用できません。
(スポーツで例えるならば...... 2部リーグでは2部リーグでの戦い方があるため、2部リーグで長い間訓練してもトップリーグで通用する選手にはなれません。選手は早々にトップリーグに上がって、トップリーグで活躍するための技術を身につけるべきです)