論文誌とは、学術雑誌、学術ジャーナル、学術誌と呼ばれています。英語ではjournalもしくはacademic journalです。
Wikipediaによれば論文誌とは…
「主として研究者の執筆した論文を掲載する雑誌」だそうです。
まさにその通りですが、他にも知るべきことがあります。この記事では、論文誌に関する重要なことを網羅的に説明します。
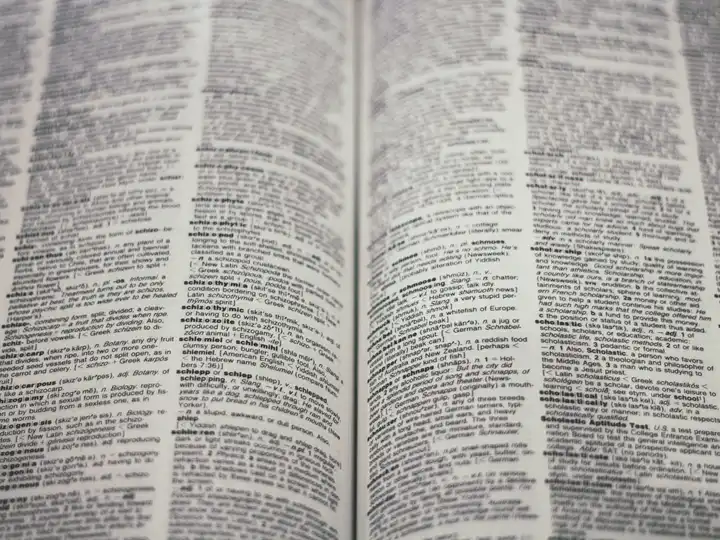
論文は論文誌から出版された原稿です。「論文誌」について知りたいですか?
この記事では、(1)論文誌とは何か、(2)有名な論文誌は何か、(3)論文誌同士にどんな違いがあるのか、さらに(4)最近の問題、について紹介しました。
これから論文を書く人や、そもそも論文って何だろうか知りたい人は必読です。
ちなみに、この記事は「論文誌」だけにフォーカスした記事です。「論文に書くべき内容」について説明していません。また、論文とは論文誌の査読を合格した原稿なのですが、「査読とは何か」についても書いてません。論文に関する疑問を網羅的に知りたい人は、まとめ記事 [論文とは何? 論文誌って? 査読って? 論文に関する疑問に答えます!]を参考にして下さい。
論文誌とは、学術雑誌、学術ジャーナル、学術誌と呼ばれています。英語ではjournalもしくはacademic journalです。
「主として研究者の執筆した論文を掲載する雑誌」だそうです。
まさにその通りですが、他にも知るべきことがあります。この記事では、論文誌に関する重要なことを網羅的に説明します。
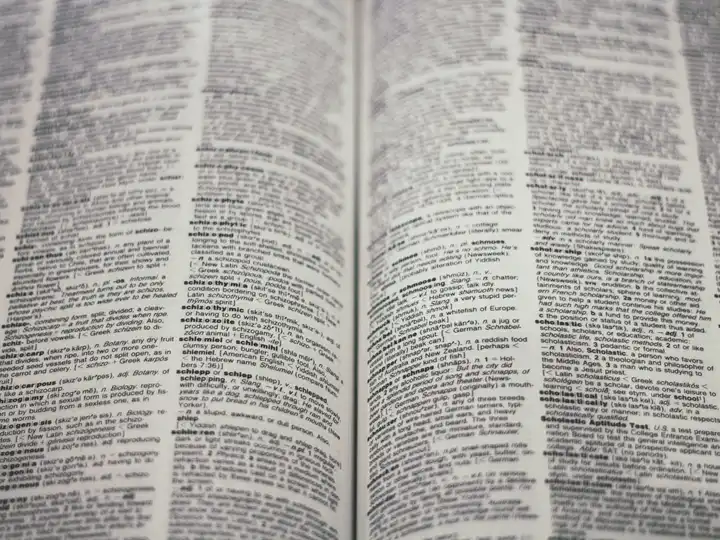
有名な論文誌として、The Lancet、Cell、Nature、Science、Nature MaterialsやNature Communicationsなどの Natureシリーズがあります。これらの雑誌は有名なだけでなく、どれも影響力のある雑誌であり、これらの論文誌に掲載されるのは科学者にとって非常に名誉なことです。他にも無数の論文誌があります。論文誌の数は年々増加しており、2010年くらいではだいたい20,000誌くらいあるのではないかと言われています。後で説明しますが、論文のオープンアクセス化の影響で論文誌の数は爆発的に増加していて、具体的な数は誰も把握しきれていません。
それぞれの論文誌には、必ずスコープがあります。スコープとは、その論文誌が目指す雑誌の内容です。例えばNature communicationsのスコープは以下の通りです
[nature communicationsのスコープが書いてあるサイト]
読んでみると「Nature Communicationsは、生物学、健康科学、物理学、化学、地球科学、社会科学、数学、応用科学、工学の全分野における質の高い研究を掲載するオープンアクセス型の学際的ジャーナルです。本誌が発行する論文は、各分野の専門家にとって重要な進歩を表すことを目的としています。」といったことが書いてあります。これを満たす内容の原稿をNature Communicationsに投稿すれば出版してくれます。

論文誌には編集者(エディター)がいて、エディターが原稿を選んだり出版したりします。エディターは原稿を受け取ると、まず読んでみて、掲載してもいいかもしれないと思ったら、次に研究者に意見を聞きます。これを「査読」と言います。
査読の最初のステップとしてまずエディターは、何人かの査読者を決めます。査読者は、大学の教授や、研究所の研究員などです。研究者はある日突然メールが届いて査読を依頼されます。
(* ちなみに査読者に給料は発生しません。全てボランティアです)
査読では、(1)実験の手法は妥当か、(2)比較すべき過去に行われた類似の研究を全て記載しているか、(3)結果から結論を導く論理に誤りがないか、といったことを吟味します。
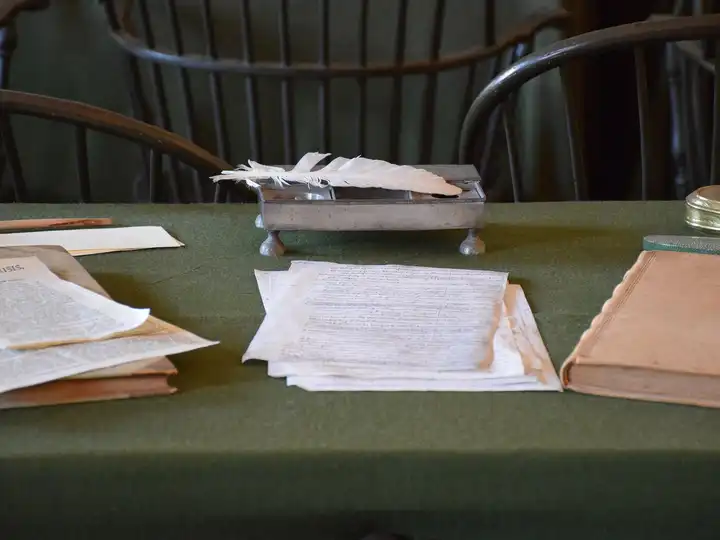
論文誌ごとに、スコープ以外にも重要な違いがあります。それはインパクトファクターです。ざっくり言うと、インパクトファクターとは、「論文が他の論文から引用される平均の数」です。有名な雑誌ほど多くの読者の目に触れる機会が多いので、有名な雑誌ほどインパクファクターは高くなる傾向があります。
インパクトファクターとは、論文誌の価値と言っていいです。原稿を書いたら、できるだけインパクトファクターが高い論文誌に採択されるように努力しましょう。
身の回りにインパクトファクターが高い論文誌に論文を投稿す必要はないと言っている研究者はいるかもしれませんが、その人の意見は聞かなくていいです。それは多分ただの言い訳です。その人は論文の書き方が分かっていない人で、つまり「科学とは何か」を分かっていない人だと思います。その人の書いた論文を見てみて下さい。良い論文を書いていないはずです。

有名な論文誌の出版社に、The LancetやCellといった論文誌を出版しているエルゼビア(Elsevier)や、NatureやNatureシリーズを出版しているシュプリンガーネイチャー(Springer Nature)があります。出版社は、出版社が出版している論文を自由に読める契約を大学と結びます。
近年この契約料の高騰が問題になっています。例えばエルぜビアが2018年にカリフォルニア大学に対して提示した契約は、5年間で57億円だそうです。契約を結ばない大学が出てきて、それに対して現れたのがオープンアクセスの論文です。オープンアクセスは論文の著者が論文誌に掲載料を支払うことで、大学や読者は契約料を払うことなく論文を読むことができます。
するとハゲタカ論文の問題が出てきました。掲載する論文数を増やしたい研究者と、掲載料をもらって原稿を出したい編集社の利害が一致した結果、お金を払えば簡単に論文を採択される論文誌が現れました。論文誌の数が増え、低品質の論文が爆発的に増えています。
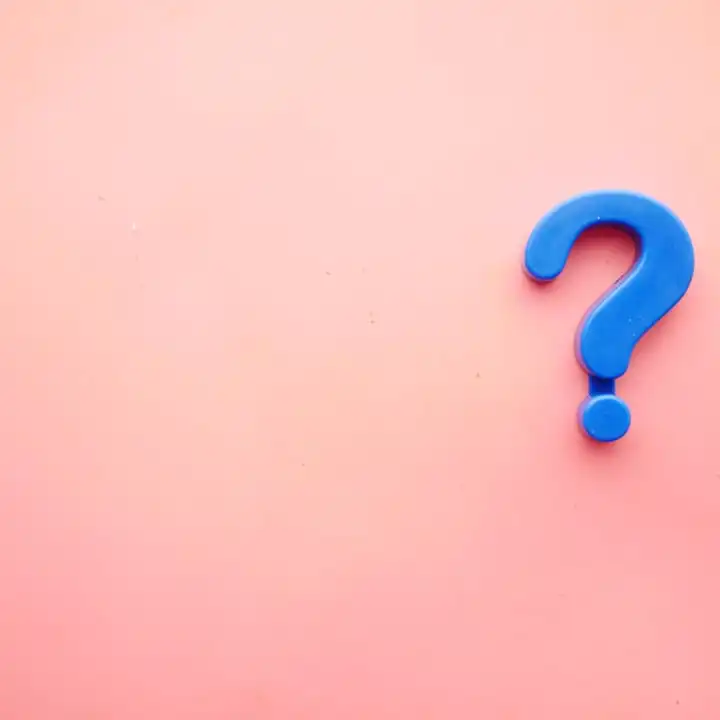
論文誌とは、論文を出版する雑誌のことです。
有名な論文誌として、The Lancet、Cell、Nature、Science、Nature MaterialsやNature Communicationsなどの Natureシリーズがあります。
論文誌にはエディターがいて、エディターが原稿を選んだり出版したりします。
エディターは原稿を受け取ると、まず読んでみて、掲載してもいいかもしれないと思ったら、次に研究者に意見を聞きます。これを「査読」と言います。査読を合格すれば原稿は論文として出版されます。
論文誌にはインパクトファクターという数字があり、有名な雑誌ほどインパクファクターは高くなる傾向があります。インパクトファクターとは、論文誌の価値と言っていいです。
2010年くらいから、出版社が提示する契約料の高騰している問題と、ハゲタカ論文が現れて論文の信憑性を担保できなくなっている問題があります。
・今回の記事では「査読」についてほとんど説明しませんでした。実際はこの査読というシステム非常に複雑です。投稿から採択までの全ての手順を網羅的に説明した記事がありますので、少しても論文を書きたいと思っている人は、必ずこの記事を参考にして下さい[論文が査読されて掲載されるまでの全ての手順]
・Nature Communicationsに採択された原稿に、解説を付けたテンプレートを作りました。Webサイトの解説した内容が実際にどう論文に反映されたか実例を見ながら理解できます。研究者として上を目指したい方、ぜひ参考に。
論文の解説付きテンプレート、なぜ重要なのか?
・論文の書き方は教わりましたか? このWebサイトに書いてある高インパクト論文の書き方をスライドにして1つにまとめました。論文の "型" を自習する教材として最適です。ぜひ参考に。
高インパクト論文の書き方をどう自習するか? [結論:この解説付きスライドを読もう]