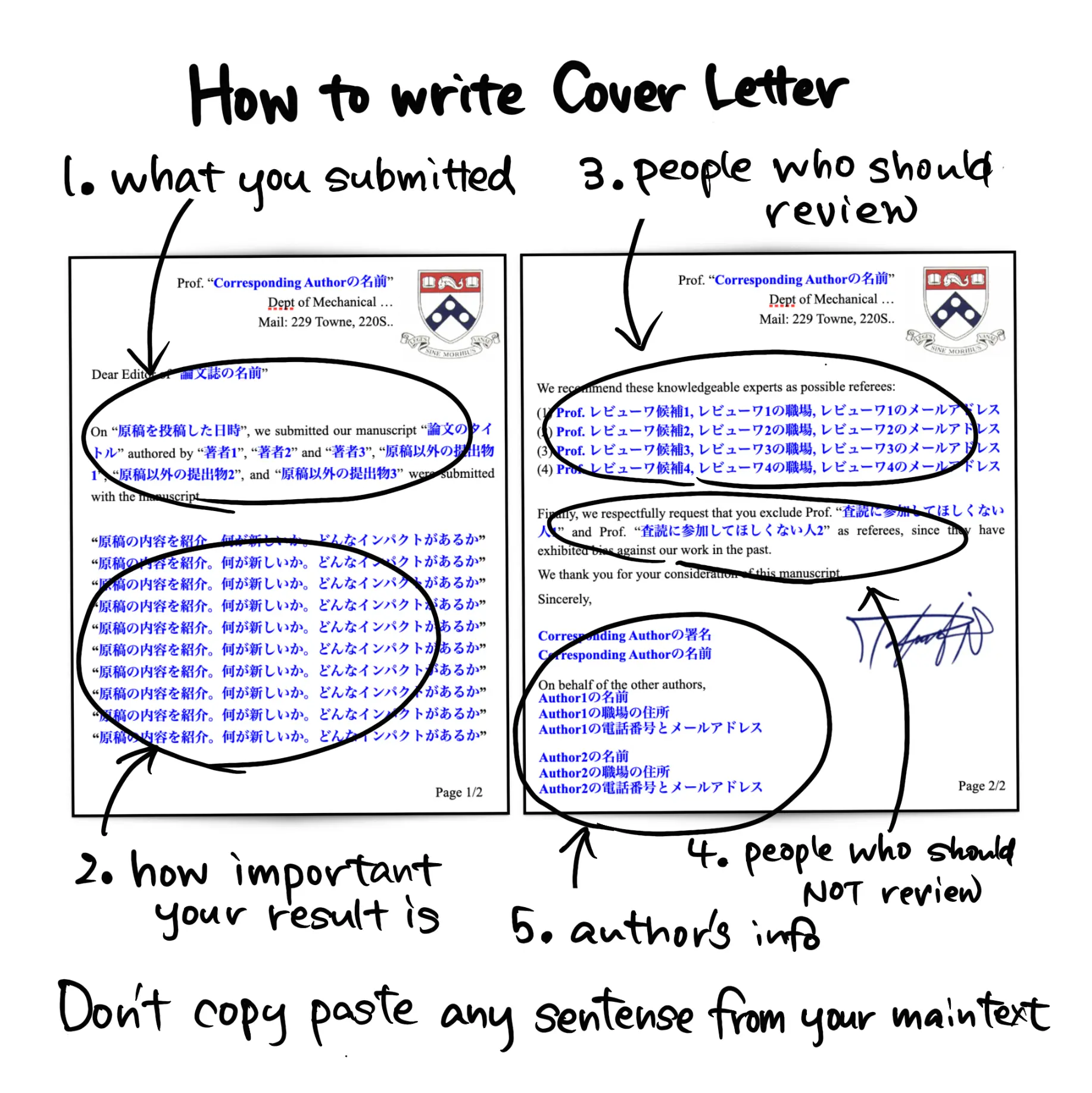論文誌のスコープは簡単に確認できます。
例えばnatureの場合なら「nature aims scope」「nature scope of the journal」をgoogle検索して下さい。
今回は例として、ultramicroscopyという論文誌を見てみましょう。「ultramicroscopy aims scope」と検索すると、簡単にAbout the journalの記述を発見できます。[このサイト(ultramicroscopyのAbout the journal)]に辿り着けます。